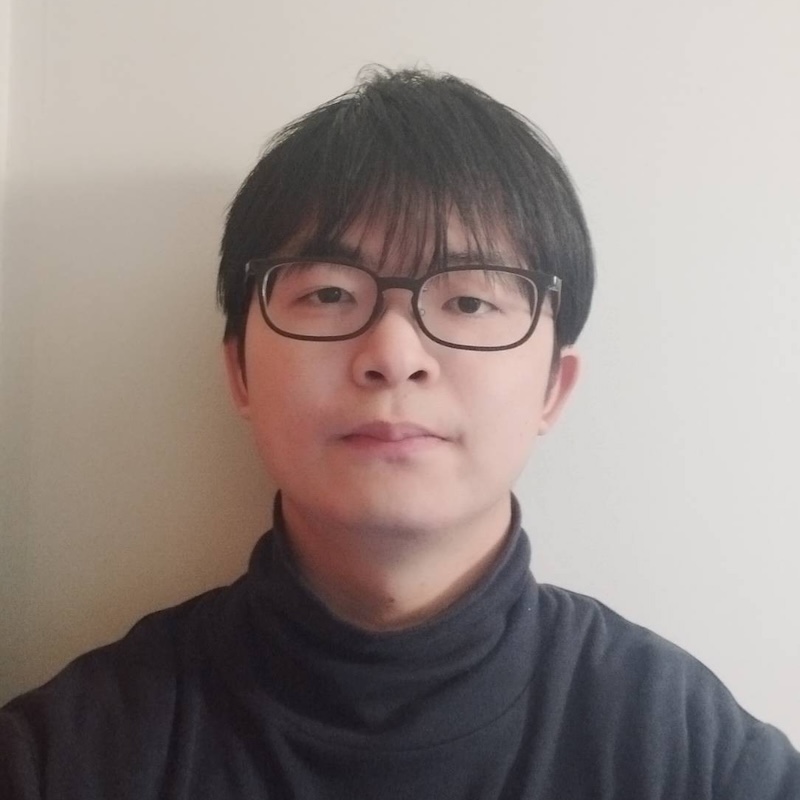北村 祐稀
- 研究科
- 情報科学研究科
- 専攻
- 情報システム工学専攻
- 専門分野
- 情報教育
- 所属学会
- 情報処理学会
- 職歴・学歴
- 2017年4月〜2020年3月 大阪府立大手前高等学校
2020年4月〜2023年3月 大阪大学 基礎工学部
2023年4月〜2025年3月 大阪大学 大学院情報科学研究科 博士前期課程
2025年4月〜 大阪大学 大学院情報科学研究科 博士後期課程
2025年4月〜 日本学術振興会 特別研究員 DC1
2025年4月〜 私立高校 非常勤講師(情報科)
- 趣味・特技
- 美味しいもの(食べる方)
- 論文・活動実績
- 【論文(査読あり)】
・北村祐稀, 岸本有生, 兼宗進, 西田知博, 白井詩沙香: カードの並べ替えを通じてソートアルゴリズムを体験的に学ぶインタラクティブ教材CardAlgoの開発と評価, 情報処理学会論文誌教育とコンピュータ(TCE), Vol. 11, No. 1, pp. 1-14 (2025).
【国際会議(査読あり)】
・Yuki Kitamura, Kazuya Hirose, Susumu Kanemune, Tomohiro Nishida, Shizuka Shirai: How Elementary School Students Experienced Algorithms: Using Sorting Algorithms Online Learning Tool, WCCE2022 (2022).
【国内研究会(査読あり)】
・北村祐稀, 長瀧寛之, 井手広康, 兼宗進, 白井詩沙香: TCP/IPの仕組みを体験的に学ぶシミュレータ教材を活用した授業の提案, 情報処理学会 情報教育シンポジウム論文集, Vol. 2024, pp. 124-131 (2024).
・北村祐稀, 長瀧寛之, 井手広康, 兼宗進, 白井詩沙香: 初学者を対象としたTCP/IPの仕組みと重要性を体験的に学ぶシミュレータ教材の開発, 情報処理学会 情報教育シンポジウム論文集, Vol. 2023, pp. 249-253 (2023).
【国内研究会(査読なし)】
・北村祐稀, Henderson Tracy, 白井詩沙香, 長瀧寛之, 辰己丈夫, Bell Tim, 浦西友樹: ニュージーランドと日本の高等学校における情報教育の比較のための予備調査―授業見学と教員インタビューを通じて―, 情報処理学会 研究報告コンピュータと教育 (CE), Vol. 2024-CE-177, No. 17, pp. 1-6 (2024).
・北村祐稀, 長瀧寛之, 井手広康, 兼宗進, 岸本有生, 白井詩沙香: すぐ使える! 通信プロトコルシミュレータProtoSim(プロトシム)〜実践結果2023&展望2024〜, 第17回全国高等学校情報教育研究会全国大会(愛知大会)(2024).
・北村祐稀, 白井詩沙香, 西田知博, 兼宗進, 長瀧寛之, 小野淳, 竹村治雄: インタラクティブなソートアルゴリズム演習ツールを取り入れた一般情報教育における授業実践, 情報処理学会 研究報告コンピュータと教育 (CE), Vol. 2023-CE-172, No. 16, pp. 1-8 (2023).
・北村祐稀, 長瀧寛之, 井手広康, 兼宗進, 白井詩沙香: シミュレータ教材ProtoSimを活用したTCP/IPの仕組みと重要性を体験的に学ぶ授業の提案, 第16回全国高等学校情報教育研究会全国大会(東京大会)(2023).
・北村祐稀, 岸本有生, 兼宗進, 西田知博, 白井詩沙香: CSアンプラグドを活用したソートアルゴリズムオンライン学習教材の開発, 情報処理学会 研究報告コンピュータと教育 (CE), Vol. 2022-CE-163, No. 4, pp. 1-7 (2022).
【書籍】
・情報オリンピック日本委員会 監修; 筧捷彦, 山口利恵 編修; 北村祐稀 執筆: JOI公式テキスト Pythonで問題解決 情報オリンピックに出てみよう, 実教出版 (2022).
researchmap
- 研究室URL
- 浦西研究室

Message私の研究対象は情報教育,特に高等学校の教科「情報」での学びです.「情報」は比較的新しい教科であり,教え方・学び方にはまだまだ改善の余地があります.そこで特に Web 教材に着目し,コンピュータ内部の仕組みを可視化したり,子どもたちが自律的に学習を進められる支援機能を備えたりする方法について研究しています.研究の過程で開発した Web 教材はオンラインで公開し,高等学校の先生方が集まる大会でアウトリーチ活動を行うことで,実際の学校現場へ研究成果を届けることにも取り組んでいます.また,自身でも高等学校で非常勤講師として勤務し,現場の視点を身につけています.
私の目標は,境域を超えた存在として学校教育における学びの質を高めていくことです.学校における学びは多様なステークホルダーによって支えられています.例えば,現場で子どもたちと向き合う学校教員,学校で使用される教材を提供している民間の教材会社や教科書会社,新たな教育方法を生み出したりカリキュラムを検討したりする研究者が挙げられます.そして私は今,これらすべての立場にあります.それぞれの立場で得られた知見や経験を総合し,異なる立場からの連携をスムーズにすることで,学校教育をもっと良くしていけると考えています.
超域プログラムではこれまで,専門分野の異なる履修生・超域プログラムに関わる先生方・課題を提供くださった地域の方々など,異なる立場の人々と協働し問題解決に取り組む経験を積んできました.今後も引き続き,さまざまなプロジェクトに力を合わせて取り組んでいきます.
(2025 年 5 月更新)