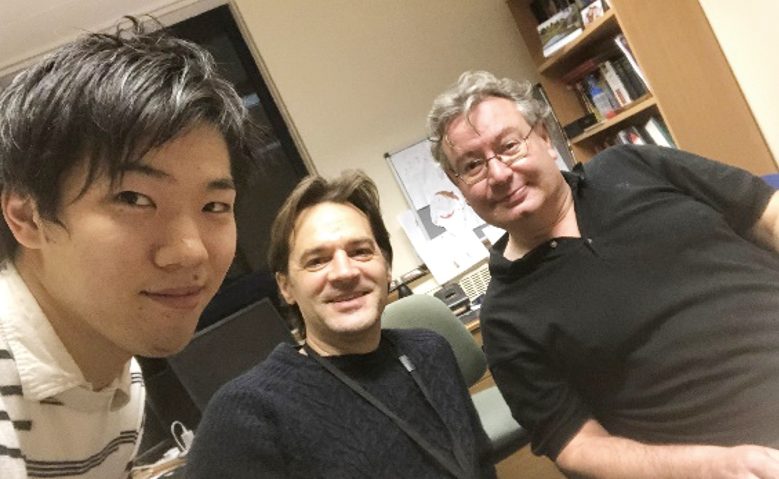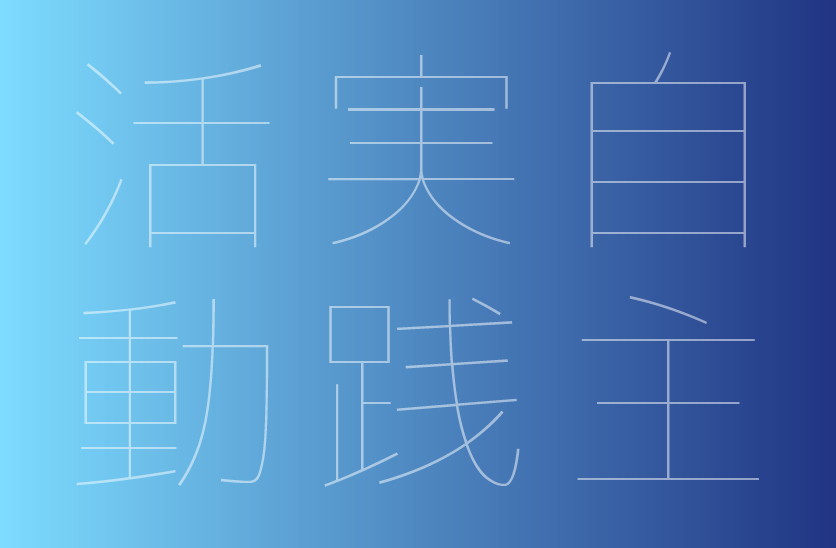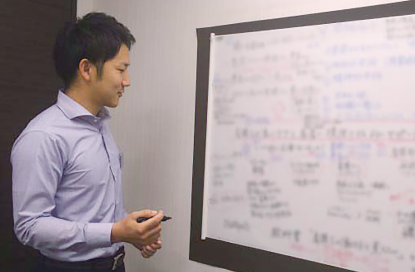自主実践活動
ICT教育の日印比較から考える ―日本の教育に向けた示唆と展望―
2025/5/2

Text: 基礎工学研究科 システム創成専攻 名取大雅
急速な技術革新とオンライン化の進展に伴い、日本の教育現場ではICT機器の活用やプログラミング教育をめぐる新たな課題が浮上しています。それは、GIGAスクール構想により一人一台のデバイスが普及しつつある一方、教員の専門性や指導法が追いついていないという問題です。
こうした背景のもと、私は対照的にICT教育が早期から重視されているインドの事例を調査し、日本の教育システムに活かせる示唆を得ることを目指しました。活動の目的は、日本とインドの教育環境や制度、生徒や教員の声を比較分析し、日本のICT教育が抱える問題点を具体的に洗い出すと同時に、活動成果の発信、公表を通じて今後のカリキュラム設計に一石を投じることです。
具体的な活動として、インド南部のバンガロールに位置する大学(Amrita Vishwa Vidyapeetham)および小中高一貫校(The Cambridge International School, Haralur・Whitefield)を訪問し、授業見学、教師や学生へのインタビュー、アンケート調査を実施しました。その結果、小学校低学年相当から週に複数回のプログラミングや情報の授業が設定されていることで、インドの生徒たちはプログラミングを身近に感じ、将来への関心を強く持っていることが分かりました。ただし、多くの授業が座学中心であり、実際にICT機器を使用した演習は限定的でした。
一方、日本国内では静岡県立浜松西高等学校や京都市立日吉ケ丘高等学校の2校に訪問し、アンケートとヒアリング調査を実施しました。その結果、日本の学校は機器やネットワークの環境が整備され、授業内でICT機器を用いる機会自体は多くありました。しかし、生徒がプログラミングの活用方法をあまり具体的にイメージできていないことが課題として明らかになりました。また、プログラミング教育を支える体系的なカリキュラムや十分な指導力を持った教員が不足しており、ICT機器が十分に活用されていない現状が浮き彫りとなりました。
このような状況を踏まえて、私はまず教員や保護者へのアプローチが必要であると考えています。生徒のICT活用やプログラミングに対する関心や理解を深めるためには、生徒だけではなく、それを教える教員や生徒を支える保護者がICT教育の意義や活用法を十分に理解し、教育の現場に適切に取り入れることが不可欠だからです。
また、活動の一環として、学習塾(株式会社しちだ・教育研究所)の職員を対象とした研究会にて、今回の調査結果を報告しました。その中で、ICT教育がもたらすメリットや具体的な活用事例について共有し、理解促進を図りました。このような取り組みが、日本国内でのICT教育推進において非常に重要になると改めて実感しました。

このように、日本のICT教育の改善には、生徒だけでなく、まず教員や保護者に向けてICT教育の意義と活用方法について理解を深めてもらうことが重要だと考えます。今後は、学生向けに活用先を知ってもらうためのワークショップはもちろんのこと、教員や保護者を対象としたアウトリーチ活動も開催していきたいと考えています。さらに、研究会や発表の機会を通じて、ICT教育の可能性を発信することで、ICT人材を育成できる仕組みづくりに貢献したいと思っています。




.jpg)