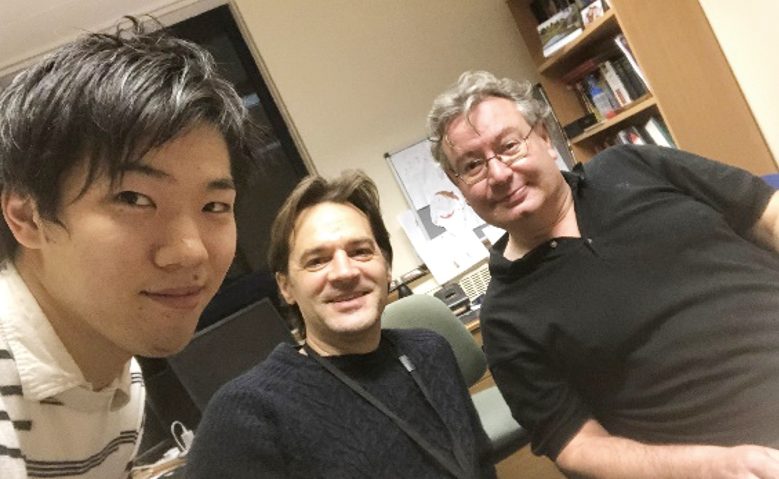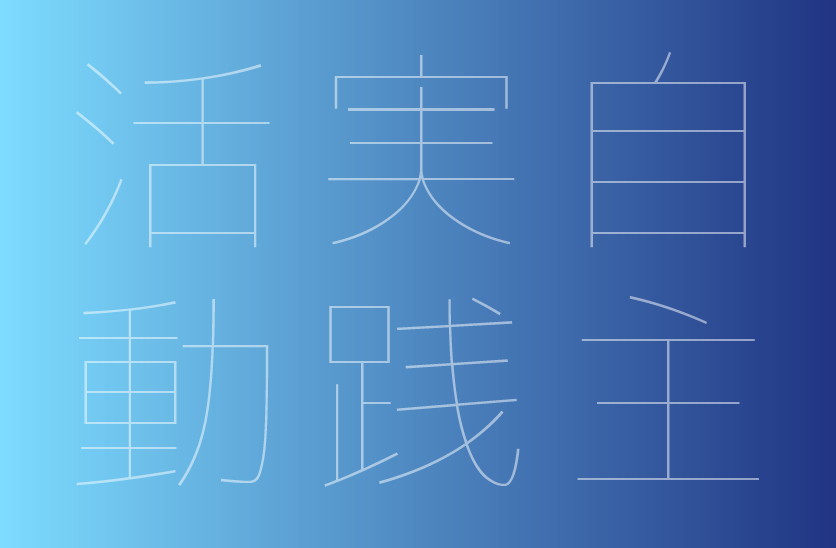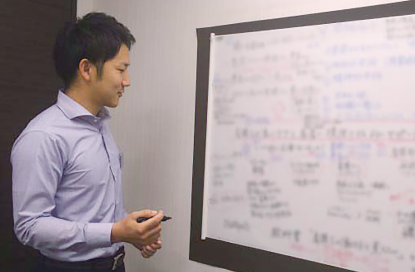自主実践活動
国内外のアロマ精油調査・現状分析に基づいてサステナブルなビジネスモデルを構築する
2025/5/2

Text: 生命機能研究科 生命機能専攻 森山さくら
私は、大学卒業後に看護師として臨床の現場に立ち、患者と向き合う中で、通常医療だけでは十分に対応しきれない苦痛や病気予防の課題を実感した。これを契機に、アロマテラピーが補完医療として果たし得る役割に注目し、その科学的根拠を解明すべく、研究室では「ヒトの匂い受容機構と生理活性の関係」に関する研究に取り組んでいる。今回の自主実践活動では、アロマテラピーの医療応用可能性を探求し、社会実装に向けたビジネスモデルの構築を試みた。
一般に、日本ではアロマテラピーは美容・リラクゼーション目的での利用が中心であるが、近年、科学的研究の進展により、医療分野への応用が注目されている。特に、生活習慣病や認知症などの治療において、西洋医学だけでは十分に対応しきれない課題があり、補完療法の重要性が高まっている。ローズマリーやレモンの精油が認知機能低下を抑制する可能性が示唆されているなど、精油の生理活性に関するエビデンスも増えている。
一方で、アロマテラピーを持続可能な医療手段として定着させるには、多くの課題が存在する。その一つが、精油の製造に必要な植物資源の問題である。例えば、ローズ精油1kgの生産には3~5トンのバラの花が必要とされる。精油の需要増加に伴い、原料となる植物の栽培量は減少傾向にあり、供給不足が懸念されている。インド産サンダルウッドは過伐採により森林資源の枯渇が問題視されており、都市化や観光業の発展による栽培地の減少も深刻である。さらに、気候変動の影響で収穫量や品質が低下し、精油の安定供給が難しくなっている。
こうした背景のもと、私は視察とヒアリングを通じて精油生産の現場における課題を明らかにし、持続可能な利用方法を模索した。各国の特徴的な取り組みを分析した結果、日本では副産物のアップサイクルによる環境負荷軽減、フランスでは地域特性を活かした生態系再生、スイスでは合成香料の活用とデータサイエンスによる生産最適化が進められていることが判明した。特に、フランスのグラース地方は香水産業の中心地であり、香料技術がユネスコ無形文化遺産に登録されている。この地域で行われている伝統的な香料植物の栽培と環境再生型農業の組み合わせは、持続可能な精油産業の理想的な姿の一例といえる。
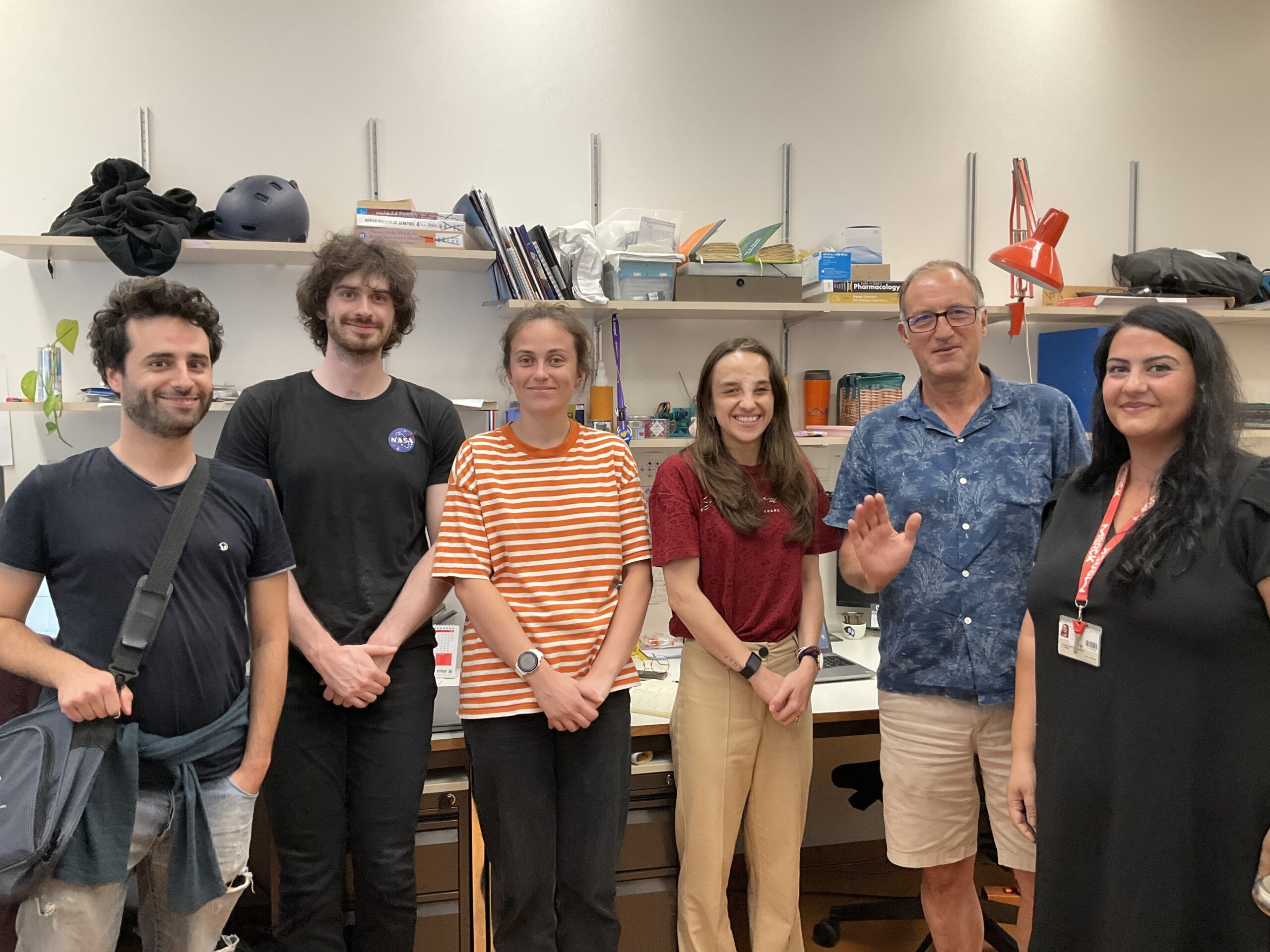
これらの調査結果を基に、私自身が新たな解決策を作成し、企業や医療機関に提案して意見交換を行った。具体的には、医療機関との意見交換を通じ、患者ケアへの貢献が期待されるとの助言を得た。また、消費財メーカーからは、精油の効果調査と付加価値商品の販売戦略の必要性が課題として挙げられ、商品開発において連携の可能性も示唆された。
本活動を通じて、アロマテラピーの医療応用を持続可能に進めるための基盤を構築する第一歩を踏み出した。今後は、研究成果を活用した実証実験を進め、医療現場での導入に向けた科学的根拠の確立と、産業界との連携による持続可能な精油供給モデルの構築を目指していきたい。




.jpg)