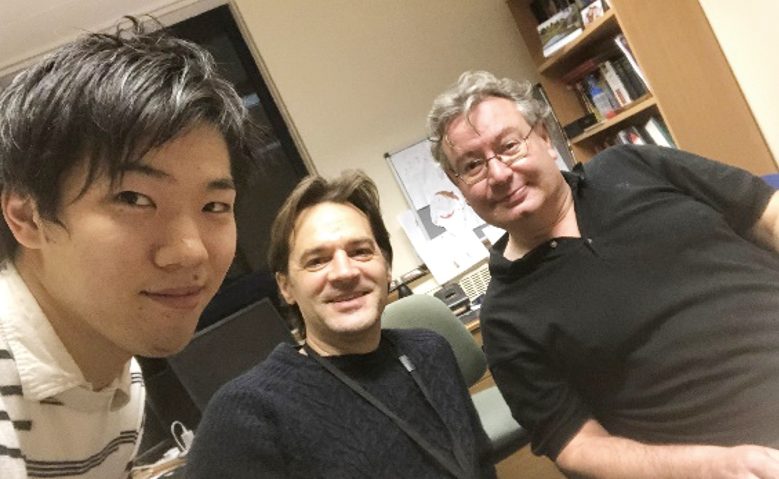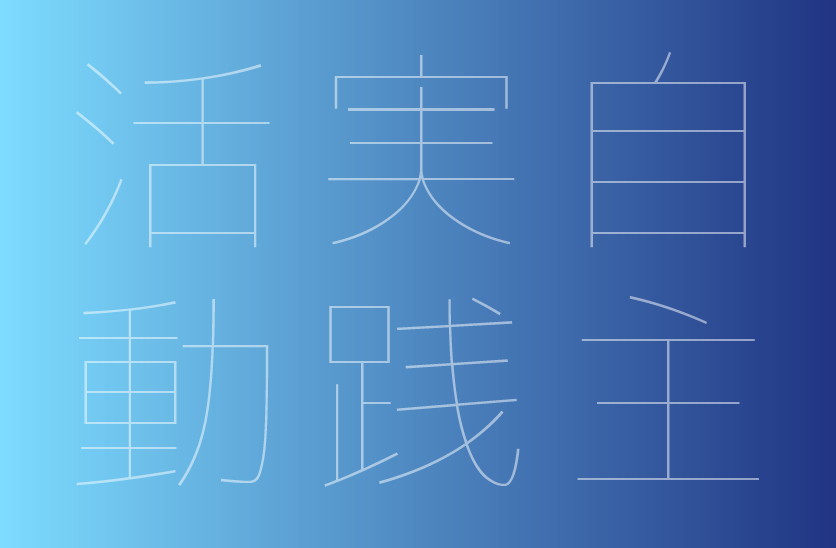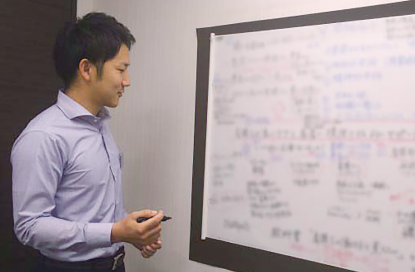自主実践活動
実践的研究者になるために―ドイツと日本における知の転換
2024/4/25
.jpg)
Text: 言語文化研究科 言語社会専攻 大津真実
移動の時代と呼ばれる今日の社会において、移民やその子どもたちの社会参画は重要な課題です。私はこれまでドイツをフィールドに、移民の母親を対象とした自治体レベルの支援事業を調査し、移民の社会統合に関する研究を行ってきました。自主実践活動では「知の転換」をテーマに、ドイツの事例を踏まえ、日本において地域の特徴を捉えた一つの支援の在り方を示したいと考えました。同時に、これまで学んできた課題解決のスキルを実践的な場で応用したいという思いも抱いていました。そこで2019年からボランティアとして携わっていた公益財団法人とよなか国際
交流協会(以下、協会)に協力を依頼し、(1)協会が提供する外国人の母親に関連する支援サービスの調査を通じて、ドイツの先行事例を土台に新しい取り組みを提案する、(2)これらの活動を通し
てネットワークを構築・強化し、現場とのコミュニケーションから立場や専門を超えて議論する力を向上させる、という二つの目的を設定しました。
活動ではまず、協会が提供する外国人の母親に関連する支援事業について、職員や外国人スタッフへのヒアリング及び活動視察を通して現状や課題を調査しました。また、現場の問題意識を明確にするため、活動の担い手である日本人のボランティアと参加者である外国人の母親を対象に、担当職員と協働でワークショップを実施し
ました。最後に、全ての調査結果を踏まえて新しい取り組みの提案を行いました。
本活動を通して、特にワークショップに向けた職員とのディスカッションや意見交換において、立場の異なる他者と協働する力を強化できたと考えます。また、既存のネットワークを起点に、新たな関係性を構築することもできました。一方で、自身に不足している視点やスキルも明らかになりました。専門や立場を超えて連携するには、初期段階に具体性のある全体像や方針を共有しておくことや、相手の立場や状況を意識して柔軟に情報を提示する能力を身につけることが必要であると実感しました。
提案の段階では、ドイツの先行事例と協会の取り組みを比較して共通点・相違点を浮き彫りにし、全体のコンセプトの中で個々の要素を検討しました。その過程で、これまでとは異なる視点から先行
事例を再検討することができ、計画段階では類似事例と捉えていた取り組みでしたが、調査後には二つの事例の差異を認識するようになりました。
両者の違いがどこから生じるのか、その要因を探るため、私は翌年にドイツに渡航し、現地の支援団体の職員に対して自主実践活動の内容を紹介しながら、ディスカッションを行いました。その結果、支援に関わるステークホルダーの違いや、
団体あるいは職員の理念・目標等が作用していることが示唆されました。
今回の自主実践活動によって、その後の国内外における研究活動は大きく前進したと感じています。同時に、異なる専門・立場の他者と協働しながら、日独間の知の転換を志す者として、本活動はそのための基本的・応用的知見を提供する機会となりました。