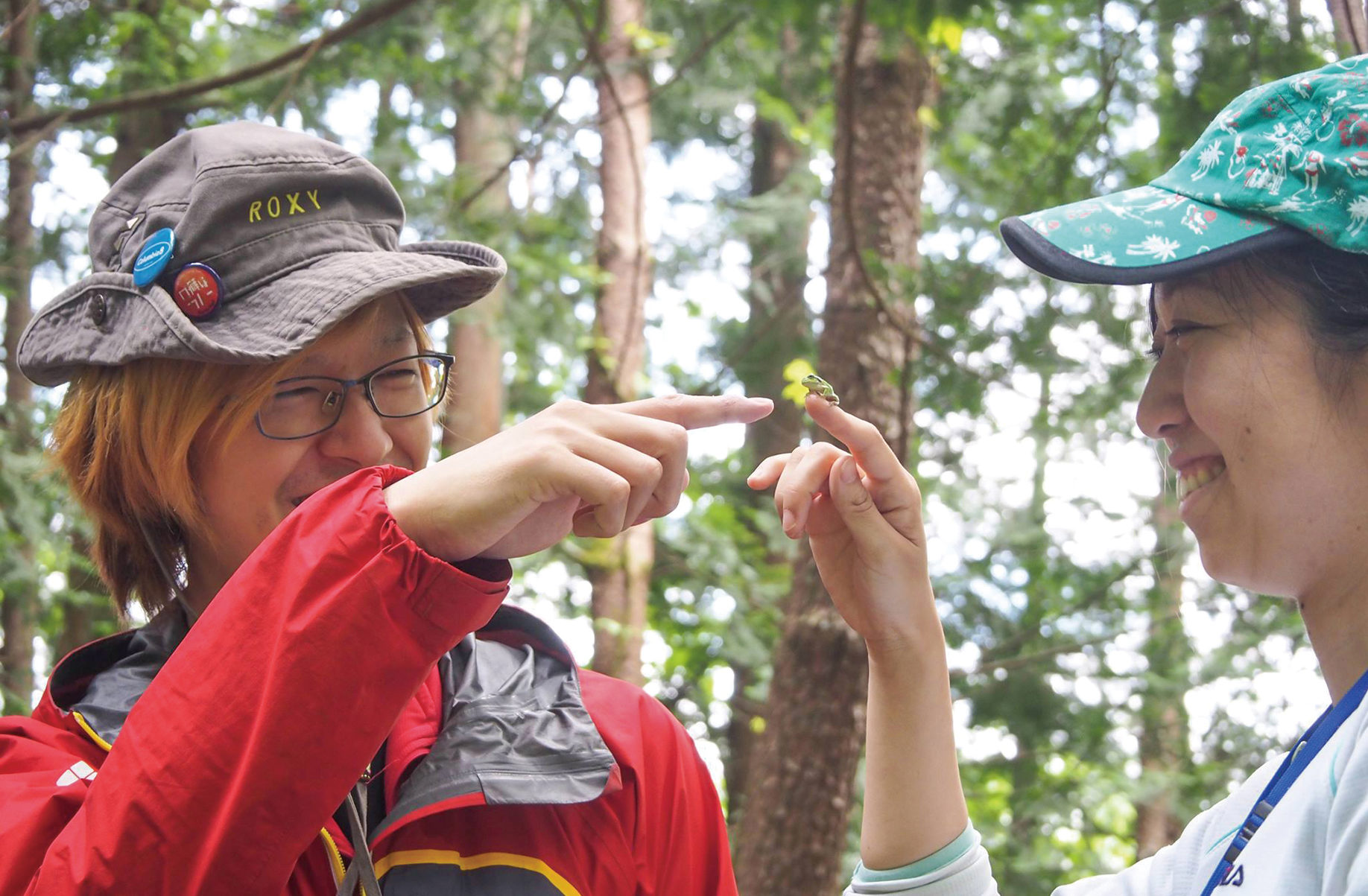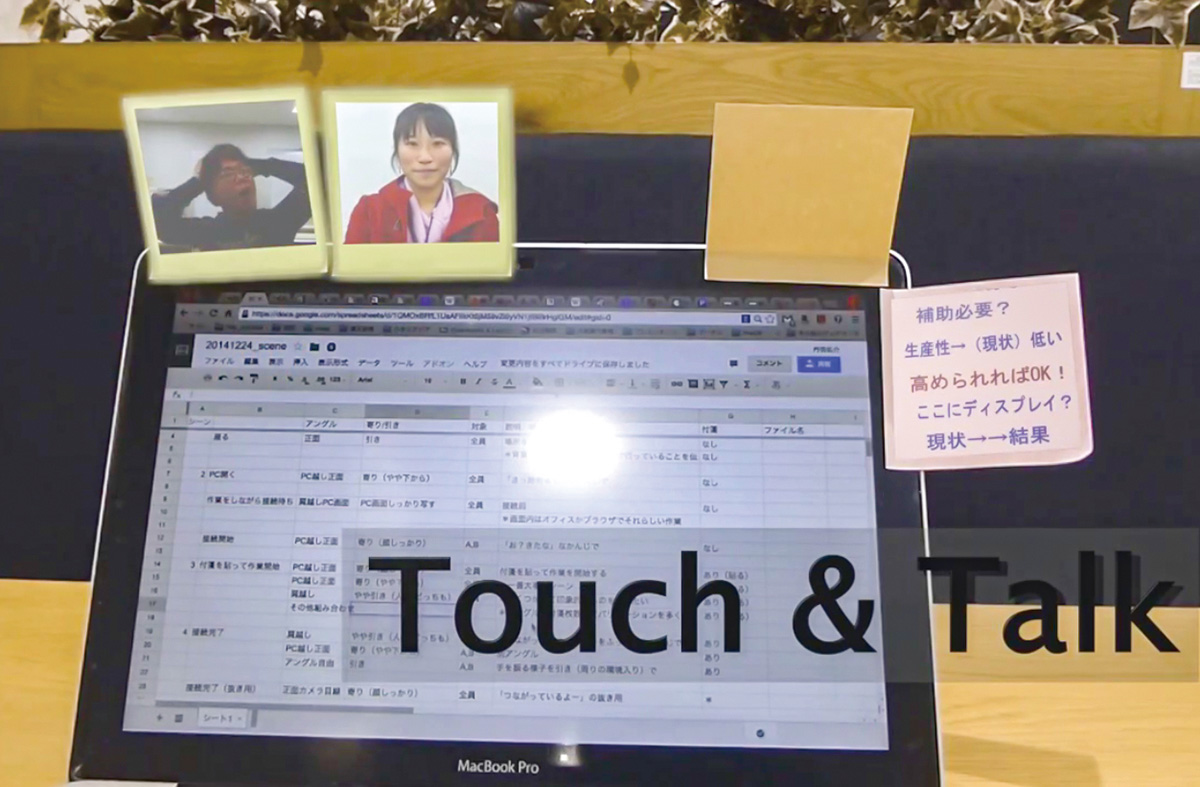プロジェクト型授業(イノベーション総合)
超域イノベーション総合:座談会「社会を考え、動かすプロジェクト」
2016/9/2

担当教員: 藤田喜久雄(工学研究科)、山崎 吾郎(COデザインセンター)、大杉卓三、大谷 洋介、渕上 ゆかり、山村麻予
Text: 花井舜平、高田一輝、篠塚友香子、鵜飼洋史、増田壮志
担当教員: 山崎 吾郎(COデザインセンター)
■はじめに
超域イノベーション総合は、超域イノベーション博士課程プログラムの3年次(博士後期課程1年)に行われる必修科目です。この科目では、これまで2年間プログラムで培ってきた知識や経験を総動員して、8ヶ月に渡るプロジェクトにチームで取り組みます。プロジェクトを通して、これまでに学んできたことを一段と深く理解するとともに、実社会の課題に自分たちなりの新しい価値提案をすること、それがこの科目の目指すところです。
2015年度は、超域プログラムの2013年度生(2期生)10名が、2つのチームに分かれてプロジェクトを実施しました。今回は、そのうちの一つ、京都市右京区にある旧京北町(以下、京北地域)の行政(右京区役所京北出張所)、及び地元のNPO(京北コミュニティビジネス)と協力しながら行ったプロジェクトの内容を紹介します。

京北チームの課題
今回、授業に協力いただいた京北地域の担当者から提示された課題は「京北地域の振興につながる「空き家」対策を提案せよ」というものでした。大阪市とほぼ同じ広大な面積をもつ京北地域は、その93%が山林で、北山杉に代表される林業の盛んな地域として古くから知られてきました。しかし、近年の少子高齢化、地域経済の縮小、都市への人口流出、さらなる過疎化の進行という悪循環のなかで、行政もNPOも、地域振興にとりくむうえでさまざまな課題に直面しています。
履修生たちが約1年間、どんなふうにこのプロジェクトに取り組み、そしてそれを通じて何を学んだのかを、プロジェクトを振り返る座談会の形式で聞いてみました。
■1. 課題を(再)定義する
山崎: 今日は忙しいところ、集まってくれてありがとうございます。今日来てくれた鵜飼君、篠塚さん、高田君、花井君に、来られなかった増田君を含めた5人が、京北チームのメンバーですね。まずは、超域イノベーション総合(以下、総合)の授業に約8か月間(4月~11月)取り組んだ感想を聞かせてください。4月にはじめて課題をみたときは、どう感じましたか?
高田: 1年前に、「超域イノベーション展開(以下、展開)」というプロジェクト型の授業に取り組んでいたので、総合も同じような感じで、みんなでワイワイ議論しながら進めるのかなと想像していました。ただ、どんなアウトプットが求められているのかと考えると、8か月と期間も長いので、なにか「超域的」で斬新な空き家活用方法を考えなければいけないのかなと思っていました。
篠塚: 最初は「空き家」という言葉から、ひとつの家、ひとつの空き家という狭いスケールで課題を捉えていたので、例えば、ある家が「空き家化」する過程に含まれる要因などを考えていました。でも進めていくにつれて、過疎化が進む地域の状況だとか、空き家問題に関わっている人たちそれぞれの意図だとか、もっと大きな枠組みで考えないといけないことがわかってきました。
鵜飼: 僕も最初は「そこに空き家がある、それをどんな風に使うのか」ということだけを考えたらいいのかなという、わりと単純なイメージで捉えていました。空き家の使い方を考えて、それを提案すればいいのだろうと。
花井: 自分の実家の近隣にも空き家があるので、この授業を通してその空き家についても考えてみたいなと思っていました。ですけど、そもそも「空き家とはなにか?」というところがよく分からなかった。年に一回、お盆のときに帰ってきて使うだけでも空き家なのかとか、人によって捉え方が随分違ってきますし。徐々に、思ったより簡単な課題ではないことがわかってきましたね。
篠塚: 私達のチームは、課題を捉えなおす(課題の再定義)までにかなり時間がかかったのだと思います。
高田: 空き家とは何か、というテーマでブレーンストーミングしてみたりしたね。斬新な「空き家」定義が出てきたり(笑)。
山崎: 課題を定義しなおさなければ、という気づきがどこかであったのですか?
篠塚: 展開の授業でシステム思考を実際に手法として体験していたので、必要なプロセスとしては意識していました。でも、具体的にそれが自分たちのプロジェクトにとってどういうプロセスなのか、うまくイメージできないまま時間が過ぎていってしまった感じでしょうか。課題を定義したと思っても、あれ、元の課題の意図と違ってしまってないかな、みたいな。長期間のプロジェクトを回した経験がなかったので、どうも実感が掴めず、自分たちの決定に自信がもてなかった。
高田: もし僕らが斬新な提案を生み出せたとしても、結局は実行の段階で上手くいかないんじゃないかと、どこかで考えていました。斬新な提案だからといって、それが有効な提案であるとも限らないですし。それに、実際に現場に入ってみたら、空き家対策を自分たちが考えて提案したところで、それがそのまま受け入れてもらえるかというと、必ずしもそうではないなという気づきもありましたね。そこから、実際に現場で受け入れられる提案をするためには「課題を再定義する必要があるな」という風に考えました。
山崎: 「空き家対策」という課題について考えるためには、その前段階で考えなくてはいけない事、課題が生み出されるプロセスを考えなくてはいけないということですね。個別の対処療法的なアイデアで勝負をするのではなくて、広い視野で課題を俯瞰しなければいけないのだと気がついて、取り組み方が何か変わりましたか?
花井: まずは情報を集めようと思い、がむしゃらに現地調査をしましたね。調査をしていると調査の仕方、調査の目的がよくわからなくなってきました。そこで、現地調査やフィールドワークの仕方について、学内で関連するテーマを研究されている専門家の意見をお聞きしたいと思い、文学研究科の堤研二先生に助言を頂きました。
篠塚: 地域コンサルの専門家や堤先生のお話を聞き、自分たちがどのような立場で、誰のために、誰に対して提案をするのか、そういうことをチーム内で明確にしないまま現地調査をしていたと気づかされました。自分たちがどういった立場で地域の人と関わって、自分たちに何ができるのかを考えるようになったのが、私達のプロジェクトにとっての転換点だったように思います。それまでは、情報だけは沢山集まりましたけど、その膨大な情報をただ整理しているような感じで、なんとなくこの辺りが着地点だろうというのが見えてきた頃にはプロジェクトも後半にさしかかっていました…。

■2. プロジェクトを通して学ぶ
山崎: プロジェクトのイメージをつかむまでに時間がかかったようですが、それまでは大変だった?
高田: プロジェクトの半ばくらいまでは「まだ情報が足りないから判断できないんだ」とみんな言っていたように思います。だから、どんどん調査してどんどん情報を集めないと方向性は決められないだろうなって。そして集まった膨大な情報を処理するのに精いっぱいで、でもまだ足りない気がして。どこかで、「よし、ここまでの情報で一度提案までもっていってみよう」という決断をしなくてはいけなかったんですが、その踏ん切りをつけるのが難しかった。
篠塚: 議論が堂々巡りしている感覚は自分たちの中でもありました。情報はどんどんたまっていくけれど、議論は全く進んでいないっていう。堂々巡りしている議論がいつも同じようなところに行きつくなという感じ、たぶんこれがこの課題の本質だろうという感覚はあったのですが、なかなか決断できなかった。私がリーダーなので決断しなければいけなかったのですが、不確定要素が多い段階で、チームの合意のもと決断するというのが本当に難しかったし、恐怖ですらありました。
鵜飼: 最初は、「具体的な解決案を考える」みたいな局面があって、その次に「課題を捉えなおさないと」と思い始めたんだよね。で、それはしばらく続いて、篠塚さんが言うように、議論を進めていく中で「この辺が怪しい」と思う箇所はいつも同じだというところに行き着くようになった。それで、じゃあそれを掘り下げて解決するためにはどんな奇想天外なアイデアがあるのか、とやっぱり考えていました。でもあるとき、この問題点を改善するだけならそこまで奇想天外なアイデアは必要ないんじゃないかと、当たり前のことを当たり前にできるようなアイデアさえあればいいのではないかと冷静に考えることが出来るようになって、そこからグンと議論が進んでいったという感じですかね。

山崎: プロジェクトに取り組んでいるときに楽しかったことや大変だったエピソードがあれば教えてください。
高田: 現地に足を運んで、普段、大学では出会えないような人たちと話せたのは楽しかったです。例えば、おーらい黒田屋の人たちは、大学に所属しているだけでは絶対に会えない人たちですよね。世間にはこんな考え方をする人がいるのかという新鮮な驚きがありました。大学内で行われている議論が、いかに視野の狭いものだったかという感覚をもつことも出来ました。まあ後々、地元の方々の気持ちがわからず、苦しむ原因にもなるのですけど。でも全体としては、地域の人たちと関われて楽しかったですね。
鵜飼: 僕は滋賀県の田舎出身だったからか、地域の方々の考え方は意外と予想通りというところもありました。子供のころから両親の姿を見ていたから、田舎には田舎の複雑な状況があるというのも実体験として感じていましたし。高田君と違ってそこは結構すんなりと受け入れられたかな。でも楽しかったですね、懐かしいというか。
篠塚: 大変だったことは、課題を再定義するまでの混迷期ですね。先ほども話しましたが、議論が堂々巡りになって、次第に「前に進んでいないのでは」ということだけをチームのみんなが共有するというような状態になる。でも、どうしたらその状況を抜け出せるのかは誰にもわからなくて、この時期は本当にしんどかったですね。今思えば、プロジェクトの全体像が掴めていなかったんだと思いますが。
花井: 毎週、授業時間外に集まって議論をしていましたが、延々と結論が出なくて、みんなイライラしていましたね。チームが破綻するまではいきませんでしたけど。やってる感覚はあるけど進んでいない、頑張っているのに結果が出ない、そんな感じでした。
篠塚: あるときは、先生方に提出する週報に「高田と篠塚がケンカ」って書かれてしまいました!ケンカではなくて、意見の相違があって議論していただけですけど、白熱してしまって。
高田: 本当にこの時期の議論はしんどかったですよ・・・夜になるとお腹がすいてしまって。お腹がすくと僕、イライラしてしまうんですよ。
鵜飼・花井: そしてお腹が満たされるとケンカ?も終わるという。最終的に、ミーティングには食事を持ってくることになった(笑)
山崎: このイノベーション総合の授業は、大学院の3年目に受講する、集大成的な位置づけで設計されています。プログラムのカリキュラムとして考えた場合に、実際に受けてみてどんな授業だったと思いますか?
篠塚: 超域のカリキュラムを見ると、「超域イノベーション導入(序論)」から始まり、順次、プロジェクトを回すのに必要な視点や方法論を学ぶようになっている。ですが、実際にプロジェクトを長期間回すというのは初めての経験だったので、授業で学んできたことを活かせたかというと、少し疑問です。暗中模索なところもあったし、次にどうすればいいのかがわからない局面がいくつもあって。学んだことをダイレクトに使用するのではなく、自分たちの向き合っている課題に応じて、さまざまな情報や手法を組み合わせて使わなくてはならないところも難しかった。そして私の場合は、専門研究で参与観察型の調査を実施しているので、たまに現地を訪問して、関係性もまだ構築できていない状態でインタビューをして、そこでの語りをデータとして扱っていいのかと考えたりもしました。
高田: 篠塚さんが言うように、総合の前に色々な授業で、調査方法や分析方法の要素は授業で学んでいたのですけど、その意図がその時にはつかめていなかった。総合のプロジェクトの後で振り返ってみると、あの授業の意図はここだったのかな、というのがわかってくる。総合の後にもう一度その授業を受け直したら、もっと学びが深くなるかなという印象は持っています。
花井: 研究や普通の授業と違って、プロジェクトになると一気に現実味が増して、関係者が多くなるのも特徴だと思います。誰かを立てると誰かが下がるし、全員が喜ぶ解なんて存在しない。それを理解した上で、その利害のバランスや、何に焦点を当てるのかを考えなくてはならない。利害関係がからむ中で、どう立ち居ふるまったらいいのかが難しいところでした。
篠塚: いま、後輩である3期生(2014年度生)の総合の授業のTAをしているのですが、TAとして少し離れたところから総合の授業を見るようになってようやく、全体を落ち着いて俯瞰できるようになりました。全プロセスを経験した後だからとは思いますが、去年は言われてもピンと来なかった先生方のコメントの意図が、今はすんなりと理解できるようになっていますね。
■3. 現場の実課題と向き合う
山崎: 地域の人たちとはどんな関わり方をしていたのですか?
高田: プロジェクトを進めるにつれて地元の人たちとの関わり方が変わってきたと思っています。最初は課題提供者の一人であるNPOの大前幹紀さんを糸口にして地域の人と繋がっていたので、大前さんに近い立ち位置の方にお話を聞くことが多かったです。中盤になると、大前さんから紹介していただいた方に紹介していただいた方、つまり、課題提供者ご本人とは少し離れた人間関係のなかで話を聞きに行くようになりました。そうなると、自己紹介から授業の趣旨説明まで全部自分たちでこなさないといけなくなるのですが、逆にいうと、このときから自分たちの意図に沿って自由にプロジェクトを進められるようになった感覚はありますね。もちろん、意図した話が聞けないということも多くはなりましたけど、想定外の方向の話が聞けたりして有益だったと思います。
山崎: 応じる相手があらかじめ決まっていると、自分の役割まで最初から決められているような感覚になってしまうからね。ということは、授業だからといってプロジェクトの仕組みを整えすぎちゃうと、逆に動きにくくなるという面もあるのかもしれません。そこは授業を設計する側も工夫が必要ですね。
花井: 時間をわざわざ作っていただいたり、本音でお話していただいたりした上、僕たちと話すこと自体を喜んでくださる方もいました。地域の方々に直接触れることで、この人たちに貢献したい、今後も関わっていきたいという気持ちがわいてきました。

山崎: 最終提案の報告会を終えて課題提供者から直接フィードバックをもらったときは、どんなふうに受け止めましたか?
篠塚: 報告会の時は、正直にいうと、あまり私たちの意図が伝わっていないのかなという印象を持ちました。課題提供者の方々は、課題を提供した時点で、こういう提案をして欲しいなとこちらに期待していることがありますよね。最初の課題文には「地域振興につながる『空き家』活用策の提案」とあったので、地域が元気になる斬新な空き家活用策という提案をしてくれるだろうと期待して報告会に来られた方もいたはずです。ですが、私たちは空き家の具体的な活用方法ではなく、行政と住民が連携する仕組みづくり(システムへの提案)と住民主体の組織が継続する支援方法(具体的な手段の提案)の二段構えの提案をしました(図1)。私たちは、「空き家」という切り口で地域について調査を進めていくなかで、空き家問題の背景にある地域の構造的な問題こそアプローチすべき本質的な課題だと定義しました。そして、空き家活用は住民主体の組織による活動を軸に進めていくべきだという立場から提案をおこなったのです。報告会は発表時間も少なかったので、提案内容をわかりやすく伝えることに意識が向いてしまい、提案に至ったプロセスをきちんと説明して、「斬新な空き家活用策を提案してくれるだろう」という聞き手の前提を切り替えることができなかった。報告会の質疑に対応しながら、「あ、伝わらなかった」と反省しました。

高田: 報告会から1ヶ月後に最終報告書の提出期限があるのですが、報告書は提案そのものを採用してもらえなくても、考え方や情報として今後参考にしてもらえるようにという意識で書きました。報告書提出後に実施した現地での報告会の時は、紙媒体で報告書を配布したのですが、それに対する反響はあったと思います。調査の過程で地元の方々の声をたくさん収集していたので、提案としてだけではなく、資料、情報としての価値も認めてもらえたように思いました。
篠塚: 最終報告書は、地元の方の声を情報として盛り込むことで、現場にとって価値のある資料になるように工夫しました。あとは、報告会ではきちんと伝えられなかった課題定義までの経緯を明確に記し、提案の必要性が伝わるよう気を配りました。現地での報告会の様子を見て、視覚化されたデータがあるとそれを介して地元の方が意見を言いやすくなるという意味では、報告書が少しは役立ったかなと感じたのを覚えています。
高田: 特に、おーらい黒田屋の方々を含め、地元の方にこの提案を伝えたかったので、現地報告会が出来たのは本当に良かったです。あまねく伝わったかどうかというよりも、伝えたい相手に伝えることができたのかなとは思います。
花井: 報告会や報告書を通して、伝わらない、伝えられない、という感情を抱くことは何度もありました。ですが、これはあくまで「提案」なので、それをどう受け取るかは受け取る側次第というところで、批判されたり拒否されても仕方のないものなのかなと思っていました。でも、批判されるにしても、まずは伝えないと始まらない、伝えるべきことは伝えよう、と思い切って発表した感じでしょうか。
高田: プロジェクトが終わってから半年後くらいに(2016年6月)京北を再訪問したとき、課題提供者の一人である片山博昭さん(右京区副区長、京北出張所長)が、僕らの提案を受け入れてくださっていたというか、実はよく理解してくれていて、議会で政策の提案するときにも参考にしたよと言ってくださったのは嬉しかったですね。結果的には、地域にとっても、課題提供者にとっても、悪くない提案だったという自己評価でよいでしょうか(笑)。

篠塚: 普段の研究では、「考える」という事は沢山していますけど、そこで考えたものが実際に動き出すところ(社会実装)まで付き合えることは中々ないですよね。でも総合の授業は、どういう提案をしたら実際に社会のなかでものごとが動くのかというところまで考えるプロジェクトです。実装の段階で色々なしがらみも出てくるので、課題に対する答えを見つけるだけでは解決できなくて、そこに関わる人たちの意図が複雑に絡み合う状況でどう動くかも考慮しないといけません。自分たちの考えたことが上手くいかない、じゃあどうしよう。こっちがダメだったからあっちを試してみよう、と。このように、社会実装まで一連のプロセスを経験できたことは大きかったです。
花井: 僕たちの活動がどれだけ地域に影響を与えたかはわかりません。でも、少しだけでも良い影響を与えたという手ごたえを、先日の再訪問のときに感じることができました。
高田: 展開の授業では、課題や目標を挙げていても、「そうはいっても学生の考えることだし短期のプロジェクトだから…」という甘さというか印象があったのではないかと思います。ですが、総合は8か月という長期間のプロジェクトだからかもしれませんが、課題を提供する側の期待もすごく高くて、「良い提案があったら本当に採用したい」ということを、お世辞かもしれないけど何度もいわれていました。それを感じて、僕たちのモチベーションは凄く上がりましたね。これがなかったら、ここまで議論は白熱しなかったかもしれない。
篠塚: 混迷期は、もうええわ、適当になんかかたちにしとけ、みたいな投げやりな気分になり、モチベーションが下がったこともありましたけどね。そういう時は先生たちのコメントに対しても、「現場の状況もわからず、なんか理論的なことばっか言ってるな」と感情的になってしまって。
高田: 下がったテンションを、ご飯と出張で上げる、その繰り返しです。ご飯は大事。3期生のみんなはちゃんとご飯食べて議論しなよ!
鵜飼: それ、高田だけやん!
■4. おわりに
2014年から実施している超域イノベーション総合は、今回が2回目の実施で、教員にとっては、まだまだ試行錯誤の途上にある実験的な科目です。この科目は、従来の大学院における授業とは、異なる点が少なくとも2つあるように思います。
一つは、専門の異なる大学院生がチームを組んで、自主的に、約8ヶ月間の長期のプロジェクトに取り組むということ。今回京北のプロジェクトに挑んだ履修生たちの専門は、それぞれ工学(環境工学)、情報科学(人工知能、知識工学)、人間科学(現象学、精神医療)、薬学(分析化学)、生命科学(細胞生物学)でした。専門が異なると、何をもって課題とし、何をもって提案とするか、どういった手段・方法を効果的と考えるか、さらにはチーム・ビルディングの仕方に至るまで、多様な価値観がチーム内に持ち込まれます。別の言い方をすれば、議論の前提を必ずしも共有できない状況が生まれて、その分コミュニケーション・コストが高くなります。しかし一方で、新しい発想というのは、凝り固まった前提が疑われたときに生まれやすいものでもあります。こうした考えのもとに実施している授業では、教員は、「知識を授ける者」であるという以上に、教育の「場を作り出すこと」に注力しているといえるでしょう。授業内での役割は、むしろ脇役であり伴走者 ──ときにメンバーの一員── といってもよいかもしれません。プロジェクトが成果へと結実するように助言をしつつも、成功も失敗も含めて学生主導でありつづけることが重要であると考えているのです。ついつい横から口を挟みたくなるのが教員の性なのだとしたら、ひょっとすると教員にとってこの授業の一番の難しさは、黙って見守っていることなのかもしれません。
もう一つの特徴は、このプロジェクトには現実の課題を抱えた当事者(課題提供者)が複数存在し、その当事者に対して、課題の再定義にまで遡って有効な提案をするという実践的なタスクが課されているということです。教育プログラムとして実施する以上、提案の採用・不採用がそのまま活動の評価(授業の成績)となるわけではありません。しかし、限られた期間、限られた予算のなかで提案を形にしなければならないということは、実社会におけるほとんどのプロジェクトがそうである以上、無視できない制約条件です。これは、長期に渡ってさまざまな形で協力してくださる課題提供者に対して、ただ一方的に教育の機会を提供してもらうのではなく、授業を通じて大学と社会の間に新しいつながりを作り出していくための仕組みでもあるのです。
履修生たちは、リアルで雑然とした「しがらみ」に直面し、右往左往しながらも、意欲を失うことなくプロジェクトを完遂してくれました。そして、課題を正確に把握することが実はもっとも困難で、そして創造的な行為でもあるということを感じ取ってくれたようにも思います。授業を作る側にとっても新しい挑戦を含んだ取り組みですが、学生たちがプロジェクトにのめり込んで活き活きと活動する姿をみるのは、「脇役」である教員にとっても有意義な経験となりました。
座談会のなかにも出てくるとおり、今回のプロジェクトがすべて終了した後の2016年6月に、プロジェクトのフォローアップとして、学生たちと京北地域を再訪する機会がありました。その際に、今回のプロジェクトの成果物が、地域振興に取り組む現場で実際に活用され、政策立案の参考資料として部分的にではあれ採用されたことを、地域の行政長から伺いました。それは、実際にプロジェクトに取り組んだ学生たちにとってはもちろんのこと、新しい大学院教育のかたちを模索する超域プログラムにとっても、大きな手応えを感じることのできた瞬間だったと思います。
長期にわたって協力いただいた京北地域の関係者のみなさまに、改めて感謝申し上げます。