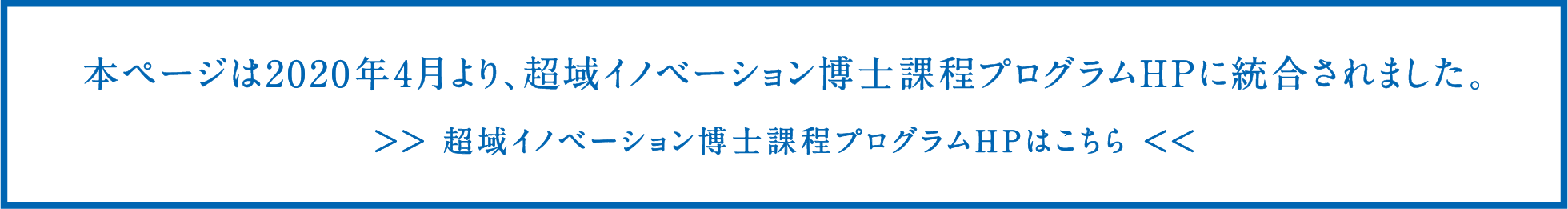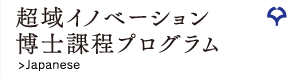授業名:超域イノベーション展開 ソーシャル・イシュー解決
担当教員:平井啓(未来戦略機構)
福吉潤(㈱キャンサースキャン)
山崎吾郎(未来戦略機構)
三田貴(未来戦略機構)
大谷洋介(未来戦略機構)
Texted BY: 基礎工学研究科 2014年度生 奥野 輔
■はじめに
「超えることでしか生まれない」とは、異なる専門分野を持つ人材が協働し、一般常識や固定観念を覆すイノベーションを生み出すという超域イノベーション博士課程プログラム(以下、超域プログラム)のコンセプトを表現したフレーズである。現代社会では専門分野の高度化と価値観の多様化により、異なる立場を持つ人々の間で対話を持つことが難しくなっている。実際に、近年盛んに議論されている原子力発電の問題を例にとると、原子力推進派と反対派の間にある価値観の食い違いから議論が議論とならないまま、“諍い”として終わってしまうケースが散見される。超域プログラムの履修生に求められることの一つとして、このような社会に存在する立場や価値観の違いから発生する断絶を超え、社会の中に対話を生み出す人材になることが挙げられると私は考える。
しかし、私は超域プログラムで履修生同士がそれぞれ自分の専門からの視点にこだわってしまい、建設的な議論が行えないまま終わるグループワークを何度も経験している。その経験から異なる背景を持つ者の間で建設的な議論を行うことは本当に難しいと実感している。それでも私は履修開始から1年半が経ち、超域プログラムで多くを学んだ今、専門分野を超えた対話を持ち、「超えることでしか生まれない」何かを生み出したいと感じていた。そんな中、今回の「超域イノベーション展開」(旧:ソーシャル・イシュー解決)を受講することになった。そこで、私は「グループ内で対話を行い、専門分野を超えた協働を実現すること」を目標として取り組むことにした。本記事では「超域イノベーション展開」の講義内容と私の取り組みを紹介し、超域2014年度生の現状や私が今抱えている考えを少しでも共有できればと思う。
■課題にとりくむ
「超域イノベーション展開」は、モジュール方式ではなく2週間の期間のうち、その期間の初め、中頃、終わりに計4日間の講義を行う集中講義型の授業である。講義の期間中は履修生が4〜5人でグループ(チーム)を組み、一つの課題に取り組む。グループは、ジェンダーや専門研究分野のバランスを鑑みて担当教員から指定されるため、講義が始まるまで誰と組むことになるかは分からない。
まず初日に、実際の案件をモデルとしたケースを通じて、社会的課題の解決策を生み出すためのデザイン思考という手法を学ぶ。その後、数人のグループに分かれて、学外の企業から提供頂いた課題に対して、ケーススタディで学んだ手法を用いながら2週間ほど議論を重ねて解決策を見出すことに挑戦した。一日目に手法を学び、二日目に集まった私たちに提示されたのは、取り組むべき課題と、6日後に中間発表をすること、そして中間発表の1週間後に最終発表を行うということだけだった。この期間、どのように課題に取り組むのか、スケジュールから使用するツールまで、全てがそれぞれのグループに委ねられたのである。

今回、私たち(稲富、小川、立山、山並、奥野)が取り組んだ課題は「10年後のある製品の新しいコンセプトを提示せよ」であった。デザイン思考に基づいて、本課題においては、
1. 製品を使用するターゲットの決定
2. ターゲットのニーズを探る
3. ニーズを踏まえた製品のコンセプト考案
4. 製品のプロトタイプ作製
5. プロトタイプをターゲットが求めるか検証
という5つの工程からなるサイクルを何度も繰り返すことにした。例えば、「40代の主婦」をターゲットとして定め、「日常的に使用するので、掃除がしやすい製品がほしい」といったターゲットのニーズを抜き出したとする。その後、そのニーズを満たす「凹凸がない製品」のようなコンセプトを定めた後に、簡単な試作品、プロトタイプを作製し、そのプロトタイプが「40代の主婦」にとって魅力的な製品になっているかを検証する。
しかし、このサイクルではターゲットやそのニーズの定義をできる限り具体的に行わなければ、議論が抽象的になり、一般的な誰でも思いつくようなプロトタイプに行き着いてしまうため、いかに具体性のある議論を行うか、ターゲットやニーズを明確に定義することが重要になる。今回の授業のために結成された私たちのグループでは、まず製品を使用する様々な人の声を集めようと、インターネットや書籍による文献調査に加え、できる限り多くの人にインタビュー調査を行った。そして、それを持ち寄って、メンバーが単独で実施した調査やインタビューを元にニーズを考えるという作業を行った。しかし、多くの人に協力していただいた割に、うまくニーズを抽出することができなかった。この他に、視覚障碍を持つ人に向けたインクルーシブデザインの視点から考える手法を取り入れるなど様々な取り組みを行ってみたものの、どれも議論に具体性がなく、良いプロトタイプを作製できそう、あるいは作製できたとは思えなかった。これは、単独で調査したものを持ち寄るときに、知らず知らずのうちに情報量が落ちてしまい、具体性がなくなっているためではないかと気づいた。また、調査で抜き出すべきニーズについても、それぞれが個別で調査を進めていくうちに多面的な見方ができなくなり、議論が抽象的にならざるを得なかったのである。
私たちはその状況を改善するために、メンバー単独で調査するのではない、別の方法を採用することにした。それは、ターゲットになりうるような人を数名にしぼりこんだ上で、メンバー数人で彼らのもとを訪ね、インタビューを行い、そのインタビューで得た情報についてメンバーで話し合って、最終的なターゲットを決める方法である。この方法では、インタビューで1次情報(ターゲット候補である人たちの「生の声」)にメンバー複数人が同時に触れることができるため、具体性を担保でき、さらにその1次情報について複数人で話し合うことで、様々な切り口からその情報を検証し、多角的な視点を持つことができた。このため、チーム内の議論の具体性が飛躍的に向上する要因になった。
■グループを失速させないために

もうひとつ、デザイン思考の肝となるのは、1つ1つの工程に時間をかけて質にこだわるよりも、短時間で何度もサイクルを繰り返し、ターゲットのニーズや製品のコンセプト、プロトタイプの質を徐々に高めていくようスピード感を持って取り組むことである。スピード感を持って取り組むためには、自分の意見にこだわりすぎず、時には相手の意見を受け入れる姿勢をメンバー全員が持ち、対話を行っていくことが重要である。そのために私が意識したのは、グループの全員が課題への参加を「義務」と感じず,自発的に「参加したい」と思えるような場、雰囲気を作ることである。 超域プログラムの履修生がグループで活動するにあたって、研究活動や超域プログラムの他の講義が重なることが多く、メンバーによって活動の参加度合いに差が出てしまう。実際、私たちのグループでも、研究活動の実験のためミーティングを抜けるメンバー、活動期間中に海外研修や出張でフィンランドとイギリスにいくメンバーがいた。このような参加度合いの差によって、グループ内の信頼関係が崩れてしまうことがよくある。例えば、私も以前、別のグループワーク中に、参加度合いが少ない他のメンバーに不満を抱えながら資料を徹夜で準備していたことがある。そのグループワークでは、他のメンバーに対する悪感情が先行し、全く建設的な議論ができなかった。
しかし、超域生は多忙であり、全員の参加度合いを揃えることは現実的な選択肢ではない。そのような状況でも、全メンバーがお互いに信頼関係を持ち、それぞれの異なる専門分野や視点を活かした議論を行うためには、グループ内でメンバーが自発的に取り組む意識を持ち、他人の参加度合いを気にしないようにする必要がある。自分が「参加したいから」活動しているのであれば、他の人が出席していないときも「自分は頑張って来ているのに、なぜあの人は欠席なのか!」と不快感を覚えることも少ない。そうすることで、相手のあら探しや自分の意見に固執せず、メンバー間で良い成果を出すために団結した議論が行えると私は考えていた。そこで、活動中は「自分は参加したいからここにいる」という私のスタンスを明確にし、他のメンバーが一人でも多く同じように思ってくれるようその思いを何度もグループに伝えた。そして、他の活動で抜けるメンバーに対しては「頑張ってきて」と前向きな言葉をかけるよう心がけた。また、メンバーがグループ内での自分の存在意義を実感できるよう、メンバーの専門やパーソナリティが反映された意見や突拍子もない思いつきが出ることを常に歓迎するよう努めた。
以上の取り組みとメンバー全員の強い参加意欲によって、今回の講義ではグループのメンバー全員が自分にできることに全力で取り組み、参加できないメンバーがいる場合はそれを補い合いながら協力することができた。さらに、お互いに信頼感があり、個人が自分の意見だけにこだわることもなく、スピード感のある議論を行った結果、デザイン思考のサイクルを何度も繰り返せたこともグループワークの最終成果物の質を高める要因となっていたと思う。
■課題の“解決策”を提示する
最終的に課題を示されてから2週間が終わる頃には、自分たちの満足度が高い提示案を考案することができた。講義の最終日に行われた最終発表会では、私たちの案について、課題を提供してくださった企業の担当者様や講義担当教員から「発想が面白い」とコメントがあり、一定の評価を受けたことを感じた。
しかし、その反面「製作コストなど実現可能性について、より考慮してほしい」との指摘があり、現実性が高いかつ画期的な案を提示できたとは言い難いことにも気づかされた。今回は、実際の製品を使う消費者をターゲットとして明確に想定し、そのニーズに基づいてプロトタイプの作製を行ったが、本講義のように実際の案件を題材にしたプロジェクトに取り組む際には、実現可能性という視点を欠かすことができないということも、授業を受けての一つの学びであった。
■「超域イノベーション展開」で学んだこと

振り返ってみて、今回の提案はグループのメンバーがそれぞれの専門領域を超えて対話することで生み出された案であったと思う。上記で述べたように、調査をグループ全員で一緒に行ったり、参加へのモチベーションを持ち続けたりという工夫のほかにも、「対話」の中でメンバーの高い多様性が議論に及ぼす好影響を感じることが何度もあった。例えば、哲学を専攻する小川歩人君が人類の歴史で火がどのような役割を果たしてきたかを詳細に話してくれたことは、私たちが取り組んだ製品の重要な要素である「火」について改めて考えるきっかけとなった。また、労働経済学を専門とする山並千佳さんの社会を定量的に捉えようとする姿勢は、他のメンバーにはない視点であり、私たちが議論を異なる角度から見ることを促してくれた。
このように今回私たちが提案した案はメンバーそれぞれの視点が集約されたものであり、対話を行うことで専門分野を超えて協働するという「超域イノベーション展開」における私の目標は達成できたと思う。一方、成果物の質は、学外の担当者様から指摘もあったように「案自体は面白い」というレベルに留まってしまっており、「超えることでしか」生まれない何かを生み出すことはできていないように感じた。しかし、私たち自身、建設的で多様性のある議論に取り組めたことで活動中は常に充実しており、今後このように全員が協力するチームでより長い期間取り組むことができればいつかイノベーションを生み出すことができるかもしれないと思える2週間であった。
来年度、私たちは「超域イノベーション総合」の講義で実際に社会にある社会課題の解決に取り組む。その講義では、専門分野を超えるだけでなく、超えることで本当に価値のあるものを生み出すことを目指したいと思う。