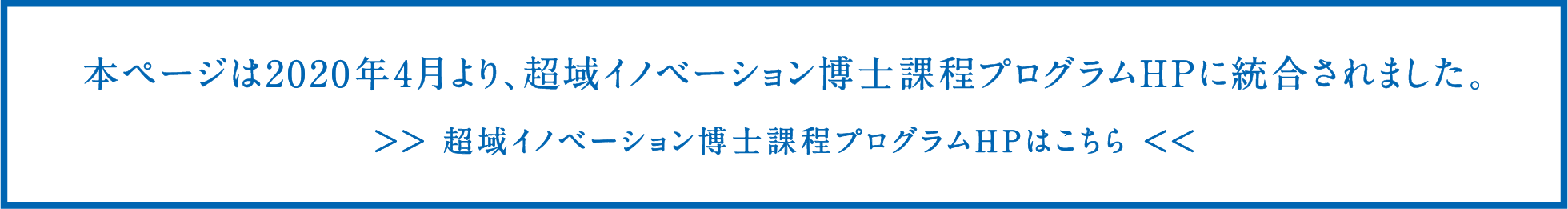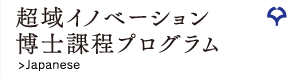Texted by 大阪大学大学院法学研究科(超域2014年度生)常盤 成紀
われわれブータン国民は……いつのときも、ブータンの主権を強固なものにし、自由がもたらす恩恵を守り、正義と平穏を確かなものとし、そして、われわれのもつ絆、幸福、善き人生を高めてゆくことを、ここにかたく誓う。……
ブータン王国憲法 前文
「うわさの」ブータンへのフィールドスタディは、まさに“百聞は一見に如かず”の旅路であった。ブータンという国は、特にある時期を境ににわかに知名度が上がって以来、しばしば勝手なイメージで語られることが多い。はたしてブータンは理想郷か、それとも未開の地か。「幸せの国」に入り込んだ報告者の気づきの旅をたどる。
■ ブータンの民主化
ブータンの民主化は大変興味深い。いまから遡ること7年前にブータンは民主化を行ったのだが、それは国民の意思ではなく、先代の第4代国王の意思に基づくものであった。現在は第5代国王のもとで議会を置く民主的立憲君主制が敷かれているわけであるが、国民の多くは、この政体の変更に納得していない。なぜならば、ほとんどすべての国民は国王と国王の政治を深く信頼しており、王制を廃止する必要を感じていないからである。同時に、国民は民主主義を個人の利益誘導と党派対立の温床とみなしており、民主主義のその側面を本質的に悪だと考えている。他方、仏教の影響から、共同体への参加と責任の引き受けを重んじる思想があり、それと民主主義を重ね合わせる考え方もある。代表的な知識人であるダショー・カルマ・ウラもその一人であり、またCNR(College of Natural Resources:ブータン王立大学農業カレッジ)の学生にもそのように考える者がいた。彼らは、民主主義の悪い側面を理解しながらも、民主主義を歓迎している模様である。だが大多数の国民は、「国王が大切だとおっしゃるなら」ということで民主主義をようやく受け入れているという。
これは民主主義/デモクラシーの本家ヨーロッパとはかなりの違いがある。まず、民主主義やデモクラシーは、まず理念系では、市民からのムーブメントによって政治的に勝ち取るものであって、国王は民主化を望まないというのが基本的な発想である。そして実際にも、被支配階級からの変革によってもたらされたケースが多い(だが実際にはその被支配階級も、別の切り口で見れば支配階級か特権階級であることはよくあることであるが)。それにもかかわらず第4代国王はみずから王制を廃止し、立憲君主制に移行させた。これにたいして“Democracy from Above”(Aim Sinpeng, “Democracy from Above: Regime Transition in the Kingdom of Bhutan.” (2007). Journal of Bhutan Studies 17: 21-47.)と表現された論文が驚きをもって発表されるなど、ヨーロッパ的な常識から見てこれは特異な現象である。
また、同じくヨーロッパの基本的な考え方からすれば、民主主義は個人の自由や権利を政治に反映させるシステムである。もちろん古くはギリシャ、アテナイの時代には、市民は公的な事柄に関心を寄せ、共同体の価値を達成するために政治参加することこそがデモクラシーの基本であると考えられていた。しかし近代のヨーロッパでは、完全にそれと取って代わられたとまではいわないにしても、選挙による代表制と、党派ごとの利益獲得競争でもって民主主義を理解することの方が主流である。これと比べたとき、参加と責任を軸とするブータンの民主主義はかなりアテナイ型のデモクラシーに近い印象である。ブータンの有権者が自らの一票の有効性をどこまで感じているかはわからないが、代表制民主主義の政治においても政治家は個人ではなくコミュニティを代表しており(これはエドマンド・バークを彷彿させる発想である)、投票による政治参加であってもそれは個人の利益誘導ではなく共同体全体への参加であるという発想が一定の割合を占める社会は、個人主義の強いヨーロッパで一部の知識階層が長らく夢見てきた、それこそ理想郷ですらあるように思う。この現象を、「ヨーロッパ的な視座」からどのように理解することができるのだろうか。
■ いつまで続くのだろうか
ブータンの特徴は、まるで理想郷の姿である。民主主義は理性的に理解され、共同体への参加と責任が何より尊重される国。またそのほかにも、国民の幸福が政策の軸に掲げられ、環境の保護や王権の制限は憲法に定められ、医療や教育は全額無料である。なぜブータンはこうであることができているのであろうか。
大きな理由の一つが、仏教思想の共有であろう。国民のほとんどすべてが仏教徒であり、仏教を中心とした文化、思想が国民に根付いている。仏教の精神に根差した政策に目立った反対がないのは、おそらくこのためである。また、共同体の規模やそこからくる国民同士の近さも理由として考えられるであろう。ブータンの人口は70万人強であり、吹田市と豊中市を足したほどの人口である。小さな共同体では共和制が成立しやすいと考えたのはシャルル・ド・モンテスキューであったが、これは一定程度説得力があるようにも思える。
だが、別の要因として、情報社会や貨幣経済が未発達であること、ならびに本格的な政治的、経済的不安を経験していないことが考えられるかもしれない。ダショー・キンレイ・ドルジは対談の中で、ブータン内に流入する情報を統制するつもりはなく、しかしながら流入した情報をどのように扱っていくかは真剣に議論しなくてはならない、と話した。実際にCNRの学生たちもみなスマートフォンをもっており、帰国した今でも彼らからFacebookのメッセージが頻繁に飛んでくる。彼らは、国内にモノがなくても、世界レベルの情報の大海原に、すでに投げ込まれている。ダショーとしては、情報の整理は智慧や理性の問題かもしれないが、その智慧や理性もまた情報の影響を受けることは避けられない。そして海外への興味が消費欲求に変わっていくならば、それに応じて生活の中でキャッシュが必要になってくる。いまはまだ完全な貨幣経済でなく、バーターシステムによって生活が多くの地域で成り立っているが、今後本格的に貨幣経済に移行していくとすれば、国際経済から見たブータン国政府やブータン経済の脆弱性は高まるだろう。
そしてブータンは、90年代には反政府運動がある程度激化したものの、それ以降本格的な政治不安、経済不安を経験していない。だが、今後かりに政権交代や大規模な政治的動乱が起こったり、貨幣経済が成熟に向かったり、もしくは人口構造などの変化で国家財政が不安定化したりすることで、いわゆる政治不安、経済不安がブータンを襲うとしたら、いまの牧歌的な政治、文化はどこまで存続することができるであろうか。たとえば、消費社会の成熟と貨幣経済の完成は「持てる者と持たざる者」を生み出すが、国内に貧富の差ができれば、民主主義を通した党派対立が起こる可能性はきわめて高い。そうならないように産業や貿易を統制するような計画経済までブータンは実行するのだろうか。また、仏教はそういった状況をクリアーするほどの強力な思想となり得るだろうか。ダショーたちの国のかじ取りは、今後ますます真価を問われることになるだろう。

■ ブータンから学ぶためには
それでもなお、ブータンには日本をはじめ世界が学ぶべきことがたくさんある。水力発電によるエネルギー確保、環境保護政策、物質的成長からの決別、共同体の尊重、戦争反対、責任意識に基づくシティズンシップ、家族愛、社会や他者への信頼。世界がこのブータンのコンセプトに憧れを抱いたことは事実である。環境破壊、経済不安、テロや戦争の恐怖、社会的閉塞感、相互不信の人間関係、競争社会。近代化のフロントランナーとしての先進国、およびその追随者たちは今、自らの残した多くのツケを払わなくてはならない局面に来ており、さもなくばその先に待っているのは決定的な破局かもしれない。そうした中で、このような流れに与せず、持続可能な社会を指向する国ブータンは、なるほどシャングリラと思われても仕方ないほど、とりわけヨーロッパやアメリカには魅力的に映ったことだろう。もちろん欧米や日本は自滅を潔しとしているわけではなく、なにか手立てを打ちたいと思っている。その一つは技術革新や創造的破壊、いわゆるイノベーションだろう。しかしそれだけではなく、人びとはなにか違う世界観や思想を求めたいとも思っている。それはアジアの山岳国家、ブータンにあった。
こうした思想的欲求は、現代に特別なことではない。いつの時代にも人類は、どこか別の集団がもっている思想に、自分たちの改革の可能性を賭けてきた。それは自由主義であったり共産主義であったり、共同体主義であったりした。だが、どの思想移植においても継受者たちは、元のものをそのまま取り込むことはできなかった。ソヴィエトはカール・マルクスの思想を当時の文脈におきかえたし、アメリカの共同体主義もまたアテナイの時代のポリス思想をそのまま採用したわけではなかった。
よって、たとえばブータンの民主主義があくまでブータン版民主主義だったように、日本がブータンから何かを取り入れる際にも、もし言葉を与えるとすれば、それは日本版ブータニズムとならざるを得ない。ブータンは民主主義を、ヨーロッパからそのまま移植するのではなく、ブータン用にアレンジを加えて運用している。日本でもその昔、福沢諭吉や西周(にし・あまね)は、日本の近代化のために日本に西洋的なものを取り入れようとしつつも、完全に日本の文脈に翻訳しきれないものと格闘し続けたという。明治初期の日本のような危機意識でもし今の日本がブータンから何かを取り入れようとするならば、今の日本を見つめ、これからの日本に本当に必要なものは何か、という軸から、ブータンの達成した価値の本質的な部分について検討を加えていかなくてはならない。憧れは鏡である。
■ おわりに
ブータンは幸せの国ではない――このいい方は多くの純朴な人々の期待を裏切り、また、同じ数いるであろう粗雑な批評家たちを満足させる。しかし、おそらく世界中のどこよりも、自分たちにとっての幸せとは何かを真剣に考えている国である。
ダショー・カルマ・ウラは、文化について、それは自分たち自身を記憶するもの、「メモリー」であると教えてくれた。物流や情報、そして何より競争原理と成果主義によって、われわれは今、とてつもないスピード感の中で生きている。しかしダショーにすれば、われわれは往々にして、せかせかした日常の中で自分自身を見失ってしまっている。ここでスピードは「忘却」と結びつけられる。他方、文化や慣習は、そのスピードを緩めてくれる働きを持っている。宗教的な慣習、伝統的な文化は、いつも変わることがなく、ある時期、ある条件になれば、いつも同じことが繰り返される。その繰り返しは、目まぐるしく変化する日常の中で、その変化から切り離された、スピードのない世界を作り出しており、そのゆったりした生活は、われわれに自分自身をしっかりと見つめさせてくれる。ダショーはこのように文化や慣習の持つ役割を理解したうえで、スピードが忘却をもたらすならば、スローはメモリーをもたらすものだ、と述べた。
欧米に起源を持つ文明発展には、不測の事態にたいして自然をコントロールすることで対処しようとする発想(科学主義)や、個人の選好を所与のものとする発想(自由主義)に勢いを与えた側面があるということは否定できないだろう。それは、一方で、結局のところ自然を完全にはコントロールできずにいわゆる「リスク社会」を発生させ、他方で、民主主義的決定の手続きにかんするルール以外に個人を拘束することができない「決められない社会」を発生させたといえる。
これにたいしてブータンの人びと(そしておそらく仏教文化圏の人びと)のとった方法は、自然ではなく、自分自身をコントロールすることであった。彼らの文化理解はそれを物語る。もちろん、ディヴィッド・ヒュームが見出した人間本性としての情念を否定することはほとんど不可能であり、いい意味でも悪い意味でも、人間の歴史はあくなき向上心の結果である。だが、――かりにヒュームの親友アダム・スミスが見出した「自然」が洋の東西を問わない概念であるとすれば――人間社会には「進歩」と同時に「調和」が必要であり、ブータンの文化は、その「調和」の側面を照らし出しているようにみえる。また、西洋においても、科学技術が人々の生活を加速させたのは、ほとんど19世紀以降の出来事である。16世紀イングランドにおいてトマス・モアは自著『ユートピア』の中で、科学技術の進展で人びとが6時間しか働かなくてよくなり、それ以外の時間を余暇に使える世界を理想郷として描いていた。また17世紀初頭、イタリアのトマソ・カンパネッラは、人びとが科学技術によって4時間しか働かなくなる世界を夢想していた。これら、「余暇」「自然」「調和」「メモリー」といった概念には、どこか共通するところがあるのではないだろうか。
そして、彼らの中でもとりわけダショーと呼ばれる人たちを中心とした知識階層は、これからの国づくりについて、そのヴィジョン、グランドデザインを示そうとしている。GNH政策はその成果であり、彼らのコミットメントの結論である。それが達成できたのは、国王への敬愛からか、ダショーへの信頼からか、政治社会の規模ゆえか、仏教精神の共有ゆえか、それは分からない。いずれにしても日本にはない条件が働いていることは確かである。それゆえ、手放しで評価することはできないにせよ、自由主義が陥りがちな「決められない政治」にたいしては、「選択」や「コミットメント」が一定の重要性を持つということを、このことは示している。
われわれはブータンのようにはなれない。そして多くがなりたいとも思っていないだろう。いくらカントリーサイドの暮らしに憧れていても、娯楽もなく、人間関係が良くも悪くも煩雑であり、文化や宗教が生活を規定し、職業選択が限られるような世界で、いまの日本人が満足するとは思えない。また、選択やコミットメントなどというが、一部の自由を無視した社会的決定が、正義の名のもとに無条件でまかり通るような社会は、明らかに別の危険性をはらんでいる。それゆえ、ブータンを真似れば幸せになれるわけではない。 「ユートピア」という言葉が「ここではないどこか」という意味であるように、われわれはいつの時代も「幸せの国」をどこかに探そうとする。それゆえ、「ブータンは幸せの国か否か」というある意味で不毛な問いかけをしがちである。だが、「幸せの国」を探してはいけない。われわれがブータンから一番学ばなくてはいけないことは、《自分たちにとっての幸せとは何か》に真剣に向き合う、彼らの姿勢なのである。

本稿は2015年4月に書かれたものに若干の修正を加えたものである。