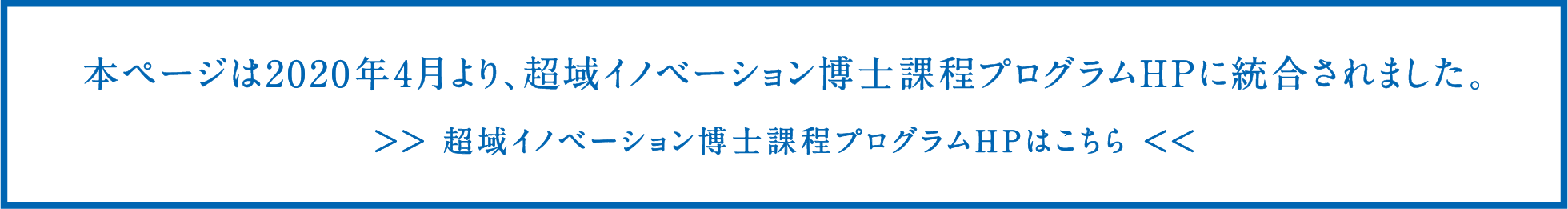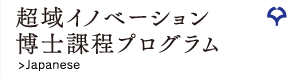■「歌会」参加者レポート
<1月28日分>
1月28、29日に大阪大学では創造性を育むワークショップ「歌会」が実施された。各講義では現代短歌の第一線で活躍している歌人が講師として登壇。短歌についての講義の後に、参加者が提出した短歌の批評を行った。
28日のゲストは穂村弘。第一歌集の『シンジケート』は短歌の口語表現を切り開いた作品集として定評を受けている。また穂村は批評の面でもその明確な評価軸が評価されている。この他にも選歌による若手育成やエッセイの執筆など、幅広い分野で活躍している。 ワークショップの参加者から「短歌はよく知らないが、普段から穂村のエッセイを読んでいる」という声も多く挙がった。
【観察力が”秀歌”を生む】
短歌というと、万葉集や古今和歌集のようなものを思い浮かべる人は多いだろう。たしかに短歌は日本の伝統的な詩型という側面もある。しかしながら、短歌はそもそも五七五七七という定型詩だ。言ってしまえば、この定型さえ守っていれば古典文学の知識が無くても短歌を詠むことはできる。
では、定型に流し込むモチーフはどのようなものを選べばいいのだろうか?穂村は次の二首を引き、短歌と日常生活での違和感の親和性を指摘した。
土の上なにかの頭がおちている それはトンボの頭だった 八汐建吾
鮮やかな毛虫が蟻に攻撃をされていた他はいつもの通勤 清信かんな
一首目は当時の中学生の作品。道端に落ちている物がトンボの頭であったという、無邪気な発見が詠われている。二首目も鮮やかな毛虫を通して、些細だがなんとも気味の悪い感じが詠み込まれている。
普段の生活では、地面に落ちている「トンボの頭」も蟻に攻撃されている「鮮やかな毛虫」も無駄なこととして見向きもされない。虫の死骸や瀕死の虫を見かけたとしても「ちょっと気持ち悪い」ぐらいに思うだけで、その存在はすぐに忘れてしまうだろう。そういった些細な出来事はいわば「ノイズ」として処理され、記憶には残らない。
しかしながら、短歌では日常に潜む、こうした具体的なイメージが共感を生むようだ。穂村は自身の著書『短歌の爆弾』において、以下の短歌作品を支えるのは、詠まれるモチーフの具体性だと指摘している。
思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみ 俵万智
シャンプーの香をほのぼのとたてながら微分積分子らは解きおり 同
頬につたふ
なみだのごはず
一握の砂を示しし人を忘れず 石川啄木
以上の作品では「麦わら帽子のへこみ」「微分積分」「一握の砂」と、主題となるモチーフが何らかの限定を受けている。もしもこれらの作品が「麦わら帽子の記憶」や「数学試験」「海辺の砂」と少しでも抽象段階を上げてしまったら台無しだろう。作品の主題となるモチーフに、何らかの限定を加えることが秀歌の構造の一つと言えるだろう。
このように、より具体的なモチーフを詠み込んだ短歌は読者の経験を引き出し、「どこかで経験したことのある」印象を想起させるのではないだろうか(実際に著者は麦わら帽子をかぶって海に出掛けた経験がないが、俵の作品を読むと、自分が”麦わら帽子のへこみ”を取っておいたことがあるような気になる)。そして具体的な感覚の切り取り方、限定の仕方が新鮮であるために、読後に一種の驚きを感じることになるのだろう。
【カテゴリーの逸脱が見られる作品】
先の項では短歌に詠まれるモチーフの特徴の一つとして、具体性を挙げた。この他にも、穂村は短歌に見られる特徴として、語が属するカテゴリーの逸脱を指摘していた。
死してなお励めとばかりに墓前に供えられたる栄養ドリンク 両角博守
この歌のポイントとなるのは「栄養ドリンク」だろう。栄養ドリンクという語彙は”飲み物”という大きいカテゴリーに属する語だ。また墓前に供えられるものは飲食物やぬいぐるみなど「故人が好きだったもの」「故人にゆかりがあるもの」であって、墓前に飲み物が供えられることに何ら違和感はない。
しかしながら、飲み物(=墓前に供えられうるもの)のジャンルに属する「栄養ドリンク」が墓前に供えられた途端に、奇妙な感じが出てくる。この違和感が「死してなお励めとばかりに」という、少し大仰な描写に繋がっているのかもしれない。
「栄養ドリンク」という単語は”飲み物”というジャンルに属しながらも、”飲み物”を内包する”お供え物”というジャンルには属さない。このように、語が属するジャンルのねじれも、短歌のひとつのレトリックにはありそうだ。
先ほどは「栄養ドリンク」という名詞が属するジャンルから逸脱した特徴を持つことを指摘した。穂村が講義で紹介した以下の二首は形容詞でのジャンルの逸脱が見られる。
ネズミ捕り四ヶ所を置くもひとつだにかかつてゐないかしこいねずみ 中村清女
大仏の前で並んで写真撮るわたしたちってかわいい大きさ 平岡あみ
一首目では「かしこいねずみ」がポイントだろう。穂村はこの歌の改悪例として「むかつくねずみ」を挙げていた。ネズミ捕りを仕掛けるぐらいなのだから、作中の”わたし”が抱いているのは迷惑だとか、困るといったマイナスの評価だろう。しかしながら、ここで作中の”わたし”はネズミ捕りにかからなかったネズミを「かしこい」とプラスの評価をしており、害獣であるネズミを形容するカテゴリーを逸脱していると言えるだろう。
また、二首目の「かわいい大きさ」では、大きさを形容する表現に「かわいい」という別のカテゴリーの語を用いている。もしも単純に「大仏」と「私たち」の大きさの対比を表現するのであれば、大きな「大仏」に対する小さい「私たち」となるはずだ。しかしながら、この作品では「かわいい」という大きさのカテゴリーから若干逸脱した形容詞を用いることで、単純な対比構造を回避している。
【新規性のあるモチーフを詠んだ作品】
短歌を支える構造として、モチーフの具体性と、詠まれる語が属するジャンルの逸脱が挙げられるようだ。この他には一体どのようなレトリックがあるのだろうか。穂村は次の二首を通し、詠まれるモチーフの新しさについて指摘した。
私は日本狼アレルギーかもしれないがもうわからない 田中有芽子
奇数本入りのパックが並んでる鳥手羽先の奇数奇数奇数 同
これらの歌に特徴的なのは、「日本狼アレルギー」という語の新しさ、「奇数本入りのパック」の手羽先(手はふつう偶数だ)という事象の新しさだろう。
この「新しさ」はそれぞれ、「日本狼アレルギー」というジャンルの組み合わせであったり、家族構成の変化によって登場した「奇数本入りのパック」という社会情勢を反映したモチーフであったりと、「新しさ」を一様に定義するのは難しい。
しかしながら、先に紹介した具体性に着目すること、語が属するカテゴリーの性質に着目することを通して、このような新しいモチーフを創造することができるのかもしれない。
【歌会レポート】
後半は穂村の司会による歌会が実施された。歌会とは短歌の批評会であり、参加者は事前に短歌を提出し、無記名の状態で批評する。一般的な歌会は5~20人で行われ、歌を提出した参加者が他の提出歌の批評を行う形態を取る。
今回のワークショップで提出された歌(詠草)の総数は58にのぼったため、司会の穂村が詠草にコメントをする形式をとった。
28日の歌会ワークショップでは「指」をテーマとした短歌が募集された。集まった歌はペンを持つ指、演奏する指、触れる指、指輪…など、詠み込まれるイメージは多岐に渡った。ここではその一部を紹介したい。
魚のごと静かな自慰に湿りたる指さきをもて灯を消しにけり
この歌での「指」は「自慰」と「灯を消す」という別ジャンルの行為を繋げている。初句の「魚」が直接かかっているのは「静かな」という形容詞だが、この「静かな」という形容詞は「自慰」という名詞、さらには「湿りたる指さき」にかかる。句としてのまとまりが美しい歌だ。
私のなかに腐敗はあってほら指を圧し当てたから黒くなる桃
私のなかの「腐敗」と黒くなる桃が圧し当てる指でつなげられている。当然ながら、桃は空気に触れて黒くなるのであって、「私」とは関係がないはずだ。しかし、作品の中の「私」は自分の腐敗と桃の酸化の間に必然性を見出す。この認識の関係は作品の中の「私」独特の認識のはずなのだが、三句目の「ほら」が入れられることで、読者も「私」独特の認識に引きずり込まれてしまう。
完全な立方体のお豆腐に挿し込む中指 震えているね
完全なものを崩す時の、ある種のカタルシスが歌われている。穂村は春日井健という耽美的な描写で知られる歌人を挙げ、完全なものを壊す時の快感がこの歌にも見られると指摘していた。結句での「震えているね」という読者に対する語りかけによって、読者も作中の「私」と共犯になってしまったような、ある種の恐ろしさを感じるのではないだろうか。
鍵盤よりはなれゆく指のしずけさにはつゆき待ちの交叉点あり
この歌では格助詞「に」の語法が特徴的だ。格助詞「に」は場所も時間も示すことができ、この作者は「に」をどちらとも取れる用法で使うことで、鍵盤から指が離れたあとの「しずけさ」と「はつゆき待ちの交叉点」という場所とも時間とも取れる語とをつなげている。
月影よ 指がきれいと言われれば指だけになって会いにゆく道
「指がきれい」と言われて舞い上がってしまう作中の「私」のテンションの純度が「指だけになって会いにゆく」という暗喩で保たれている。指というパーツ、あるいは「指がきれい」という会話の一部が「私」の全体となってしまうという、カテゴリーの超越(あるいは転覆?)が見られる。
【結びに】
今回のワークショップを通し、短歌とはどのような詩型なのかがわかりやすく、時にユーモアを交えて伝えられた。また理論だけではなく、実際に自分の作品の評をもらうことで創作の面白さも難しさも感じることができた。
当レポートの筆者は日本語を専攻としており、認知言語学に関心を持っている。今後は穂村が講義で指摘していた、短歌に見られる「カテゴリーの逸脱」がどのように読者の認知に作用しているかについて、理解を深めていきたいと思う。
最後になったが、今回講演していただいた穂村氏、このような貴重な機会を与えてくださった松行先生、また当日の運営に携わった阪大短歌会のみなさんに謝辞を送りたい。
(文責:外国語学部日本語専攻3年 佐藤祐梨)
<1月29日分>
2016年1月28、29日の二夜連続で「創造性を育む短歌ワークショップ」が開催された。29日のゲストは歌人の岡井隆。現在、岡井は短歌結社誌『未来』の編集理事長であり、自身の選歌欄を持つ。評論と作歌活動の第一線で活躍している。 前半では岡井がどのように短歌を創作し、また他の歌人の作品を批評をしているのかを通して「創造性とは何か」に対するヒントが示された。また後半の歌会ワークショップでは参加者全員がお互いの作品を批評し合った。
【短歌を通してさぐる”創造性とはなにか”】
今回のワークショップは「創造性を育む」という触れ込みがある。一般的に「創造性」や「感受性」といった言葉の定義が曖昧なまま「彼のアイディアは創造的だ」「彼女は感受性が豊かだ」という風に使用されている。しかしながら、そもそも創造性とは何だろうか。辞書の”創造”の項を見てみると、定義として「新しいものを初めて作り出すこと」あるいは「神が世界を創造すること」といったことが挙げられている。どうやら「創造力を育む」ということは「新しいものを初めて作り出す能力を育む」ことと言い換えられそうだ。
一般に芸術は創造的な行為だと考えられている。絵画であれ彫刻であれ、何かしら作品を作ること自体が「新しいものを初めて作る」ことだと言える。しかし、その芸術分野において「新しいものはなにか」を知るためには、それまでどのような手法が用いられてきたのか、現在はどのような作品が評価を受けているのかを理解する必要がある。
岡井は「模倣以外に創造なし」とホワイトボードに書き、講義をはじめた。これはフランスの詩人ポール・ヴァレリーの言葉だ。自分が良いと思った作品を深く鑑賞し、その技術を模倣するうちに自分なりの作品が創作できるようになるという。
どうやら、岡井が自身の著書『短歌入門』において「読むことは作ること」と述べているように、短歌を読むことは短歌を作ることと深い関係にあるようだ。
たしかに、短歌を鑑賞すること自体に一定の能力――”短歌リテラシー”のようなもの――が必要になる。実際に歌会の評では「作者がなぜ”は”ではなく”が”を使ったか」など、作品の批評は一字一句におよび、言葉に対する感度が必要になる。読み手はそれほどの密度の詠みが求められているのだ。
岡井は先に挙げた著作において、好きな歌を持ち、作品が心に溶け込むほどに深く鑑賞することでその語法や型についての知識が身につくと言っている。好きな作品があっても、どうしてその作品が魅力的なのかを言葉にするのは案外むずかしい。一読するだけでは、歌の大意は取れても、その作品を支えている技術まで解き明かすことはできないからだ。数ある作品の中で自分が魅力を感じる歌を選び、その魅力を口にしてみること自体が創造の入口と言えそうだ。
講義では実際に岡井が作品の読み方を通して、短歌の修辞について解説を行った。ここではその一部を大まかに紹介したい。まず、比喩表現が特徴といえる次の三首について。
感情のなかゆくごとき危うさの春泥ふかきところを歩む 上田三四二
どこかさめて生きているようなやましさはわれらの世代の悲しみなりき 道浦母都子
あおぞらがぞろぞろ身体に入り来てそらみろ家中あおぞらだらけ 河野裕子
一首目は直喩が特徴的な歌だ。「感情のなかをゆく」ことが「危うさ」の比喩に用いられている。感情に突き動かされ、つい客観的な判断が下せなくなってしまうような状況だろうか。そのような精神的に不安定な「危うさ」のなかには「春泥ふかきところ」があるという。春泥とは春の雪解けなどによってできたぬかるみのことを言う。
ここでは「ふかきところ」となっているから、より一層ぬかるんでいる状態を指すのだろう。激情が解消されるような雪解けではなく、かえってそれで足をすくわれてしまいそうなぬかるみ。この作品での「春泥」は、作中の”わたし”が実際に歩いている場所がぬかるんでいるとも、”わたし”の心理の暗喩とも読める。抽象的な事柄も、読者にとって実感が沸くようになっている。
二首目も直喩が特徴だと言える。「どこかさめて生きている」ことと「やましさ」は普通、つながらない事柄なのではないだろうか。「やましさ」はどちらかと言えば”がっついている感じ”を連想させるもので、「どこかさめて」いる感じと逆の性質を指すはずの単語だ。しかし、ここで作者が「どこかさめて生きているようなやましさ」と単語をつなげることで、作者独特の物の見方が提示されている。
三首目は隠喩表現が用いられている。「あおぞらがぞろぞろ身体に入り来」るとは、いったいどのような状況だろう?と思いながら読み進めると下の句で「家中あおぞらだらけ」とある。どうやら午後に部屋中が日差しでいっぱいになっている様子が描写されているようだ。雲の移ろいや陽の傾きが「ぞろぞろ」という擬態語を用いることで、「あおぞら」が動物のように近寄ってくるようなイメージが沸く。誰しも見たことがあるはずの室内での光景も、新しい物語のように描写されている。
これら三首、どれをとっても比喩表現が新鮮だ。それまで見出されなかった関連性が作者によって見出されている。辞書的な意味では言い表すことのできない、作者の一回限りの体験を既成の言葉によって示していると言えるだろう。描かれている事柄が作者独自の物の見方によるものだから、当然「わからない比喩」も出てくる(筆者自身、三首目は岡井の評を聞くまで歌の意味がとれなかった)。 しかし短歌においては表現と理解の間を批評によって埋めることができる。自分が「わからない」と思っていた比喩が誰かの評によって急に納得できることもあり、その都度発見の面白さを感じられる。
また次の歌のように、短歌では性愛のモチーフを詠む時におなじみの表現の型がある。
乳ふさをろくでなしにもふふませて桜終わらす雨を見てゐる 辰巳泰子
あさがおが朝を選んで咲くほどの出会いと思う肩並べつつ 吉川宏志
これらの歌はどちらも植物を通して性愛がうたわれている。一首目では作中の”私”と”ろくでなし”の奇妙な力関係が示されている。おそらく乳をやる対象が子供であれば、”ろくでなし”とは言わないだろう。”私”が乳を与えるのは恋人なのだろうか。恋人を”ろくでなし”と命名することはなかなか勇気がいるが、”わたし”にはそのようにしか相手を言い表せなかったのだろう。
それにしても、性愛をうたうにしては「ふふませる」は母性が垣間見える表現だ。ひょっとすると”ろくでなし”は母性をくすぐる人なのかもしれない。それでも”わたし”は乳に熱中している”ろくでなし”に対し、”わたし”は窓の外を見ている。熱心に乳を与えるわけでもなく、どことなく冷めている”わたし”と”ろくでなし”の関係が見事に描かれ、語の選択や命名によって、作中のキャラクターにかなり明確なイメージを呼び起こしている。
二首目は性愛の歌の一歩手前と言うべきか。淡い感情が描かれている。あさがおは朝に咲く花だが、たまたま朝に咲いているのではなく、朝を「選んで」咲いているとされている。自然に起こっている現象を必然として読み替えることで、なんとなく気がかりな人と出会ったことにも何らかの必然性を見出してしまう”わたし”が描かれている。
これら二首をまとめて性愛の歌と先に書いてしまったが、一首目と二首目とではかなり趣きが異なり、「好き」にも様々な形態があることを思わせられる。短歌は、このような感情の微妙な機微も鮮やかに描くことができる詩型と言えるだろう。書き手は記述しにくいことを記述するのに工夫をこらし、また読み手はその表現を理解するために最善を尽くすことが求められるようだ。
【歌会レポート】
前半の講義を通し、作品を深く鑑賞することが、独創的な作品を生むことがわかった。このことは裏に返すと、短歌を読む経験が少ないとなかなか良い歌は作れない、とも言えてしまう。こちらに関しては、筆者自身がかなり実感していることだ。
短歌初心者の作品はどことなく似てしまうからだ。「何を詠むか」という点では、ありがたい親、まぶしい恋人など慣用表現として定着している句をそのまま使ってしまう。また「どのように詠むか」という点では、体言止めばかりの歌を作ってしまったり、初句が副詞句ばかりになったり・・・といった具合だ。
実際に自分が他の機会で出席した歌会で「どこかで見たことがある」という評を受けたことが何度かある。この歌の表現はキャッチコピー的だ、詠み込まれるモチーフがラノベっぽい、といった批評だ。こうした評を受けた時、自分のものだと思っていた言葉のほとんどが既成の「誰かの言葉」にすり替わっている事実に驚き、少し怖くなったのをよく覚えている。
何はともあれ、深く読むという経験を積むことが肝要だ。その「読み」を鍛錬するのが歌会の役割だと言えるだろう。歌会という批評の場では、提出された歌について、自分の読み方をその場で発表する。今回のワークショップでは、実際に参加者が歌の批評を行い、それに対して岡井もコメントを行った。また司会補佐を文学部四回生の鈴木加成太が務めた。
今回はお題が「人」に設定され、さまざまな「人」を読み込んだ歌が40首集まった。作者名が伏せられた状態で歌稿が配られ、司会に指名された参加者が実際に批評を行った。ここでは詠草の中から5首紹介したい。
うつくしい冗談を言ふ人だからメイル表記も旧かなで来る
旧かな遣いのメールを受信した”わたし”は、少し呆れたように「うつくしい冗談を言ふ人だから」といっている。しかし自分自身も影響を受けて「メイル」と旧かなを遣っている。微妙な関係を捉えている歌だ。また岡井は旧かな遣いの作品を多く残している。ひょっとするとこの歌は岡井に対する挨拶をうたったのかもしれない。
仁和寺に御室の花を真似たのか少し遅れて現れるひと
京都にある仁和寺の御室の花は遅咲きの桜で知られている。待ち合わせに遅れてやってくるひとを遅咲きの桜として見立てることがこの歌の魅力だろう。相手を咎めることもなく、微笑んで許してしまうような”わたし”。なんとも風流な間柄だ。地名を歌に詠み込むことで、作者の土地に対する思い入れを感じとることができる。
数学者とその愛人が信号を無視してラブホに入っていった
「愛人」を描写するとなると昼ドラのような、ドロドロとした感じを筆者は連想してしまうのだが、この歌は平然とした調子で描かれている。毎日計算式を並べている数学者でも情事となると計算できないことも多いのか、信号を無視するほどの慌てぶりだ。淡々と描かれることで、アイロニーが効いているのかもしれない。番狂わせな愛人とそれに振り回される数学者が描かれている。
たわむれに歌よむ人に恋すまじ死してなお歌残ると知れば
先の講義にもあったように、短歌には恋心をうたった歌が多くある。歌を詠む人と恋をしてしまうと、その恋が終わったとしても愛情をうたった歌は残ってしまう。ラブレターであれば引きちぎって捨ててしまえばいいが、一度発表されてしまった短歌はどうしようもない。歌人と恋することを一種の恐ろしさとしてうたっている。筆者は文語だと少し距離感を感じてしまうのだが、なぜかこの歌に関しては実感が沸いてきて、不思議な魅力を感じた。
一人(いちにん)を愛してあれば冬の陽に時の感じをぼくは失う
先の歌と同様、この短歌も恋愛をうたったものだ。恋人といるのが楽しくて時間を忘れてしまうというよりも、恋人がいない時、その喪失感のなかで時間が過ぎてしまうような情景が浮かんだ。前半部分が文語調で少し硬い感じがする分、結句に口語の「時の感じをぼくは失う」が肉声のように浮き上がってくる。
【結びに】
今回の歌会ワークショップに参加し、普段接することがない学生や一般の方と共に批評するのは貴重な経験となった。うまく言葉にならなかったこと、慌てて言葉の意味を取り違えてしまったことばかりを思い出してしまうが、それでも自分の感じたことを言葉にすること自体に意義があるように思える。短歌を読むことを通して、テクストを精密に読み解く技術や、自分の思いを効果的に発表する技術がつくことも期待できそうだ。
また本文では触れられなかったが、岡井は歌の型として、初句を七音とした77577などの詩型の可能性を示唆していた。筆者自身、今後は音韻論や歌謡史などの面から、短詩型文学としての短歌の性質を探っていきたいと思う。
最後になったが、短歌を通して創造の在り方を示していただいた岡井氏、このような特別な機会を設けていただいた松行先生、ならびに当日の運営に携わった阪大短歌会のみなさんには感謝の意を伝えたいと思う。
(文責:外国語学部日本語専攻3年 佐藤祐梨)