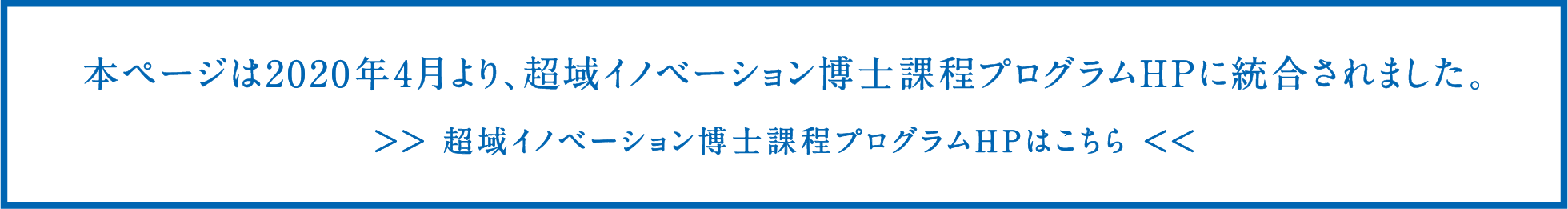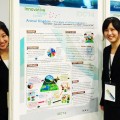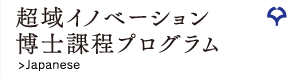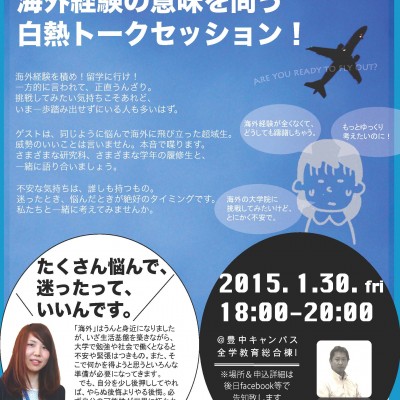授業名:超域学際・未来学I (副題:「東日本大震災」から未来を再考する)
担当教員:三田 貴 (未来戦略機構)
Texted BY: 法学研究科 法学・政治学専攻 2014年度生 常盤 成紀
本講義は、副題に「『東日本大震災』から未来を再考する」とあるように、私たちの社会がこれまでもっていた多くの前提に対して根本的な見直しを迫ることになった東北の震災を事例として、当該地域や日本社会の今後の在り方を、未来学的思考を用いて模索するという内容になっております。またここでは、座学形式による情報の共有に加え、福島から被災当事者でもあり活動家でもある方をゲストスピーカーとしてお招きし、実際の生の声を聞いて、現地の状況について理解を深めることも行われておりました。
■未来学とは
これをお読みの方の中には、「未来学」という言葉について聞きなれない方もいるかと思います。未来学とは、その名の通り未来を予測する学問ですが、それは確定的に将来をいいあてる「予知」ではないということ、単純な未来ではなくある社会にとっての「ありうべき・望ましい未来」を予測するということに、その学問の特徴があります。 根本昌彦(2008)によれば、「『未来学』は、当然未来を予測することが目的であるが、その予測はもちろん絶対に的中するものではない。しかし、外れることは問題ではない。現在の条件をもとに、未来のあらゆる可能性を考えることが大事」だとされており、畢竟、ただの将来ではなく、ある社会にとっての「望ましい未来」を、その社会の当事者の視点から予測していく、その営為に未来学の学問的価値があるといえると思います。ここでは、プロパーの未来ではなく望ましい未来を模索するという点で、社会にある複雑な関係性や、その社会の人びとの持つ様々な価値観を考慮に入れる必要があり、単純な統計結果をもって満足する学問ではないといえるでしょう。また、未来学者はその対象としての社会からすれば外部の人間であり、それにもかかわらず「当事者にとって望ましい未来を模索する」ことを目指すためには、「協働」という概念が重要になってきます。このあと具体的に述べるつもりですが、ある社会に問題が起きたときに、外部の専門家が「専門家の視点からの」望ましい未来を提示したところで、うまくコミュニケイションは成立せず、ほとんど解決には至りません。外部の専門家がその社会の未来を模索するためには、当事者の視点を理解し、協働する姿勢が必要となってきます。こういった関心から、本講義では、キーワードが「当事者の視点の理解」と「協働の可能性の検討」となっております。
■東日本大震災と未来学
日本には過去に多くの大規模な災害があり、そのたびに社会はその在り方の再考を迫られてきました。東日本大震災(以下、東北震災)もそのひとつであり、この災害は、日本社会のこれまで抱えてきた大きな前提に対して、見直しを迫るきっかけになった事件であるように思います。本稿は東北震災の評価をすることが目的ではありませんが、このあとの議論に関することをいえば、今回の震災では、専門家、とりわけ科学者と一般市民とのコミュニケイションの断絶がひとつの大きな問題となっているといえると思います。
震災前の安全神話、事件直後の情報の錯綜、現在の遅々として進まない復興。このような中で一般市民は、ほとんど科学者たちの言葉(そして行政の言葉)を信用できなくなっています。何が安全で、何が正しいのかをめぐる議論が展開される以前の問題として、専門家に対する不信と猜疑が、市民の中で先行している現状が続いているといえます。他方専門家としても、だまそうと思っている人や、市民を不幸にさせようと思っている人などほとんどいないはずなのですが、どの言葉を投げかけるにせよ市民との間でうまくコミュニケイションが取れずに困惑しているというのが事実でしょう。とりわけ科学者たちからすれば、科学的に正しいことに基づいて意見を出したり、アドバイスをしたりしているにもかかわらず市民たちが抵抗を感じていることに苦悩していることと思います。
しかし、先に述べたような「当事者の視点」にたったとき、その「科学的に正しいこと」はどこまで「当事者にとって望ましいこと」なのでしょうか。たとえば、被災者の中には、住み慣れた町や生活の一部となった仕事を手放したくはないが、放射線量などの危険性によりその場所を離れることを余儀なくされるという事実があり、そのつらさを告白することがあります。これに対してもし、ある専門家が科学的な見地から、「別の土地で生活基盤を用意するので、その心配は必要ない。こちらにくればいい」といったとして、その言葉はどういう意味を持つのでしょうか。ここにおいて科学者/社会科学者は、その本分からして「市民の生活の成立」に強い関心があり、「環境を変えたくない」という情念の部分について捨象してしまっています。ここでの「環境を変えたくない」という望みは、生活の成立を超えた、「いきざま」に関わる問題です。科学的正当性という大義のもとに提示されたある意味で無機質な言葉は、「いきざま」に後ろ髪を引かれる当事者にたいする配慮を全く欠いているがために、当事者は疎外感を覚えることになるでしょう。よって、科学者が、科学として正しいがゆえに伝えなくてはならないという信念のもとになされた発言は、不幸にも、真偽とは関係なく相手に拒否感を持たれるという結末を迎えることになります。結果協働は達成されることなく、問題は継続されることになります。
ここで書いたことはあくまでも例であり、実際にこのような無頓着なことはそこまで起こっていなかったことと思いますが、それでも、実際被災地でこれまで起こってきたこと、いまもなお起きていることは、こういうことなのではないでしょうか。専門家たちは自分たちの真価を発揮しようと意気込むのですが、価値観や思考回路が専門領域内的なものに留まってしまっているがために、問題を解決に導くどころか、その行動が当事者たちをある意味で傷つけて不信を助長し、専門家自身が問題の一要素に成り果ててしまってすらいるのではないでしょうか。もちろんほとんどの専門家は、当事者のことを考えているというはずです。しかしそれは失礼ながら、「当事者にとってはこれが望ましいはずだ」という次元で止まってしまっているように思えます。 こう考えたとき、未来学的思考は、これを一歩進める大切な思考法であるように思われます。当事者の視点に立つということは、自分自身を流動化させることでもあり、自分の声が相手にどのように聞こえているかについての想像力をたくましくさせることでもあります。そのようにして本当の意味での「当事者の視点」を獲得しない限り、協働は達成されることなく、その社会にとっての「望ましい未来」を考え、模索していくこともできないのではないでしょうか。
こう考えたとき、未来学的思考は、これを一歩進める大切な思考法であるように思われます。当事者の視点に立つということは、自分自身を流動化させることでもあり、自分の声が相手にどのように聞こえているかについての想像力をたくましくさせることでもあります。そのようにして本当の意味での「当事者の視点」を獲得しない限り、協働は達成されることなく、その社会にとっての「望ましい未来」を考え、模索していくこともできないのではないでしょうか。
私たちは今この超域イノベーション博士課程プログラムにおいて、社会に積極的に貢献していく博士人材になるべく修行を積んでいます。今回、その私たちが、専門力でもって社会に貢献するために必要となる基本的な考え方を今回、この未来学から学んだように感じました。
参考
根本昌彦『未来学―リスクを回避し、未来を変えるための考え方』WAVE出版、2008年
Hawaii Research Center for Futures Studies, University of Hawaii
Jim Dator, “Futures Studies”