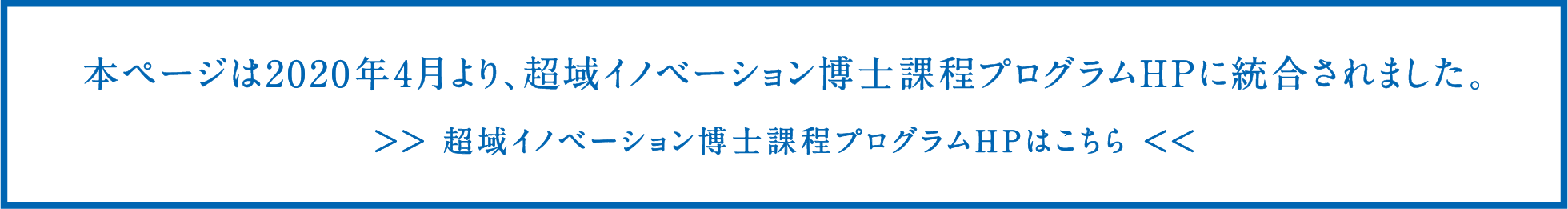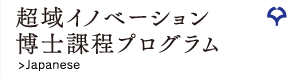>> page 1/3 はこちら >> page 2/3はこちら
Report vol.3 「超域生と仕事をしてみて」
番組終了後、制作チームの一人で学生のコーディネーター役を担当してくださった奥村太祐氏に、コメントの寄稿をお願いした。やり取りをさせていただく中で“超域”をどのように捉えられたのか、それをテレビで表現する際に工夫されたこと等を伺っている。Vol.2に記した履修生側の感想と照らし合わせながら、ご覧いただければと思う。

奥村太祐氏(地球アゴラディレクター:㈱アマゾンラテルナ)
「今回の番組制作過程を振り返り、とりわけ印象深いのが初取材時の光景です。『超域をどう取り上げようとしているのですか?』の逆質問に始まり、次々と飛んでくる意見、疑問の嵐…。私の取材人生でここまで逆質問をぶつけられたことはなかったので、正直に告白すると、かなり面くらいました(笑)。しかし同時に、スタジオの展開を考えた時に大きな手応えを掴んだのも事実です。『この光景を本番で再現できれば、相当面白い番組になる』これは、取材したスタッフ共通の感想でもありました。」
「その後、授業風景の見学やアンケートなど取材を積み重ねていく中で、学生達が次々と意見をぶつけあう場にこそ超域のエッセンスが詰まっていると改めて思い至り、『超域生が自由に意見やアイデアを出せる空間をいかにスタジオで作り上げるか?』ということを念頭に、番組内容を考えていきました。」
「具体的に考えた仕掛けは、海外の事例の一つをクイズ形式にし、超域生にアイデアを考えてもらうというものです。この仕掛け自体は何ということはない発想なのですが、演出に関してはかなり悩みました。一番の悩みどころは、『議論の過程そのものを見せるかどうか?』ということです。取材した実感で言うと、意見が飛び交うこの過程にこそ超域の醍醐味があると感じていたのですが、生放送という時間的制約がある中で、その場でお題を発表し数分で何かしらの一つの結論に至ることができるのか?について議論を重ねた結果、やはりリスクが大きいという判断に至り、事前にお題を提示し回答を考えてもらう形にすることになりました。」
「結果的には、お題を前もって提示したことで、よりブラッシュアップされたアイデアが各チームから出てきたし、スタジオの内容も盛り上がったので、この見せ方が49分の生放送という現在の番組のフォーマットの中ではベストであったと思います。しかし、議論の過程を見せなかったことで、超域とはとどのつまりどういうことをやっているところなのかが視聴者に伝わりづらかったなあという思いもあります。これは、超域生の皆さんが感じていた『自分の発言が超域のコンセプトを体現していることになるのか?』という疑問にも通じる部分だと思います。この点は、今後に向けての課題です。」
「ただ、今回の番組内容に関しては評判がとても良かったそうですし、それより何より、佐々木さんをはじめ超域生の皆さんが番組に積極的に関わっていただき、一体となって番組作りができたことが一番の財産です。そういう意味では、テレビも放送内容(結果)より制作の過程こそが最も面白い部分であり醍醐味だなあと改めて思いました。」


➢佐々木 周作/国際公共政策研究科
学生側の担当者として本番当日まで奔走した日々を今振り返ると、本当に幸福な環境下で企画に参加させていただいていたのだなあと改めて感じる。というのも、今回のプロジェクトではどの関係者も同じくらいに熱く、積極的だったからだ。そんなことは当たり前ではないかと思われるかもしれないが、現実にはそうではない状況が往々にして起こりうる。様々な面で整えられた環境を前にしても、参加者の覇気が上がらないケースもあれば、体調面での不具合が全体の盛り上がりを阻害するケースもある。幸運なことに、今回のプロジェクトでは制作側も出演者側も同じ方向性を向きながら、蜜月的な関係を構築することができた。それは一つに、vol.1に記したように、奥村さんをはじめとする制作担当者の方々が何度もコミュニケーションをとって下さったからであるし、一方でvol.3に語られているように、数ある問いかけに対し履修生一人ひとりが真剣に受け答えたからである。人の話にきちんと耳を傾け、真摯に対応し、自分たちの意見を伝えることが幸福なコラボレーションの基礎となることを学んだ。
私自身が担当者として心がけたことは、以下の一点に尽きる。できるだけ、制作側と出演者一人ひとりが直接やり取りできる環境にコーディネートすること。担当者の役割を担う手前、私自身が学生の代表として意見を取りまとめ、一人で制作側とやり取りするという体制はどの場面でも取り得た。しかし、そのようにアレンジすることは履修生の個性を知ってもらい、番組の構成に取り入れてもらうことを狙うにあたっては不適切だと感じ、少々無理矢理だったがアンケート調査などにおいても超域生全員と個人的にやり取りしてもらう方法を採った。それは単純に、私がアンケートの取りまとめをするには物ぐさ過ぎたからかもしれないが、そのような手配が制作側と出演者側の関係構築に少しは寄与したのではないかと感じる。
以上のような段階を経て、熱さと積極性を維持したまま臨んだ当日の番組出演の様子は、やはり“超域していた“のだと言いたい。“超域らしい”とは単に異なる研究科の学生が集まることや、大学と民間企業の両者が参加しているというセッティングの特徴を意味するのではなくて、異分野同士が集まった時も、双方の専門性を考慮しながら深くコミュニケーションを取り、同じ方向を目指していくという姿勢、プロセスを指すのではないか。その意味で考えると、私たちは “超域”の基本的な姿勢は少なくとも体現できていたと感じる。テレビモニターからもその様子はご覧いただけたのではないだろうか。そうであることを願い、末筆としたい。