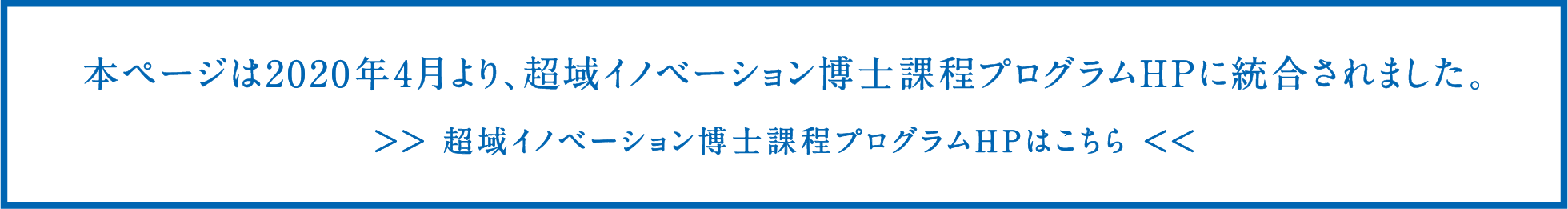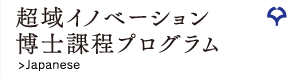Texted BY: 法学研究科 常盤 成紀(2014年度生)
Edited BY: 国際公共政策研究科 猪口 絢子(2015年度生)
Photo BY: 未来戦略機構特任助教 佐藤
紗良
すなわち、紙に書かれた思想は一般に、砂に残った歩行者の足跡以上のものではないのである。歩行者のたどった道は見える。だが歩行者がその途上で何を見たかを知るには、自分の目を用いなければならない。
アルトゥール・ショーペンハウアー『読書について』1851年(註1)
本の虫、という言葉がある。いわゆる「大の読書好き」という意味で、英語にも“bookworm”という言葉があるのは面白い。僕は今からさかのぼること二年と少し前、ちょうど修士課程二年になったころから、この超域プログラムの履修生をメインメンバーとして、読書会を開催してきた。ときには学外の社会人や、学部生、プログラム外の院生も参加することがあり、おかげさまで現在まで途切れることなく続いてきている。その主催者という立場の僕は、恥ずかしながら「本の虫」ではない。もちろん本を読むことが嫌いではないが、得意だと思ったことはないし、三度の飯よりも好きだと思ったこともない。その意味で、政治思想史を志す人文学徒としては失格かもしれない。だが、そんな僕も、本を読む、ということに魅力を感じており、またそれを「読書会」という形で続けていることに、大きな意義を感じている。今回は、とくに本の虫でもない僕が、曲がりなりにも続けてきた読書会に込めている思いを紹介したいと思う。

2017年7月の読書会の様子。
題材は松井みどり『アート:“芸術”が終わった後の“アート”』。文中に出てくるアートをモニターで参照しつつ、読んでいく。
■ 読書会とは
僕の主催する読書会では、参加者が関心のある本を取り上げ、週に一度集まり、あらかじめ決められた報告者が、担当個所について報告する形式をとっている。本の取り上げ方にはテーマ性があるときもあれば、ないときもある。報告は一回につき一章分が相場であり、ほとんどの場合報告者はレジュメをもとに進める。
振り返ってみれば、この二年の間に、ずいぶんといろいろな本を読んだ。詳しい書誌情報は省略するが、順番に並べてみると次の通りになる。:プラトン『国家』/チャールズ・ダーウィン『種の起源』/アリストテレス『詩学』/ウィリアム・シェイクスピア『ハムレット』/渡辺浩『日本政治思想史』/鈴木健『なめらかな社会とその敵』/鈴木貞美『「近代の超克」』/アラン・マルク=リウー『未完の国』/クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』/廣瀬純『資本の専制、奴隷の叛逆』/イェスパー・ユール『ハーフリアル』/松井みどり『アート』(2017年7月現在、翻訳はすべて邦題で表記)
以上のように、この読書会の特徴は、その選書の幅広さにある。それはすなわち参加者の関心の広さを反映している。人によっては、“積読(つんどく)”になっていた本を提案する人もいれば、気になっていた新刊を提案する人もいる。また、一人では読めない、いつかチャレンジしてみたかった本(とくに古典など)を提案する人もいれば、自身の専門との関連で提案する人もいる。このように関心は様々だが、みな何らかの形で本を読むきっかけが欲しくて集まっているのである。
ただ、読書会という取り組み自体は珍しくはなく、社会人のイベントとしてもよく行われている――ちなみに、社会人が自分のコミュニティを広げようとイベントを開くときのキーワードは、読書、旅行、ワインだそうだ。しかし多くの場合、それは読後感をしゃべり合う場で終わってしまう。一方で僕たちの読書会の場合は、報告者は責任をもって担当個所を報告し、もし分からないことがあれば、それを共有する。その中で参加者は、自分の理解を確かめ合いながら、内容を確認していくという作業が入る。これはいわゆる文系が“ゼミ”と呼ばれる集まりで採用している形式であり、そこには一定程度の本気さが伴う。
しかしながらもう一方で、読後感の交換や脱線といった楽しみも大切にしている。特に、参加者がそれぞれのバックグラウンドに基づいて繰り出される意見や感想は、とても面白いし、そこから思わぬ方向に議論が進む場合もある。とりわけ超域プログラムの特性上、そのバックグラウンドは実に多様であり、その多様さから生じる議論の斬新さは、ある意味でイノベーションであるともいえる。たとえば、春季集中で、渡辺『日本政治思想史』を読んだ際、幕末の開国が話題に上がったが、これをイランの「文明化」と対比させて論じる参加者がいたことは興味深かった。また、マルク=リウー『未完の国』を読んだ時にも面白い議論があった。その第一章では、以下のように論じている。明治維新前後における社会の西洋文明受容の素地を作ったのは、幕末の学者たちであり、彼らは長子単独相続社会において家業を継がなかった次男坊、三男坊であった。その彼らが相互に交流することで、当時にとって新たな知である西洋文明を受容する知識社会を形成したのだ。この、社会のメインストリームではない集団によるいわゆるアングラネットワークが新たな知的基盤を社会に構築するという知識社会学的分析は、ひるがえって現代日本における、大企業に属さないベンチャー集団による社会変革の兆しを彷彿させる。参加者たちは、江戸末期、明治初期に関する文章を読みながらも、そこにとどまらない幅広い関心で、議論を展開していった。この自由さが、この読書会の売りでもある。

■ なぜ僕たちは本を読むのか
さて、こういった知的楽しみは、ただの高等な遊戯なのだろうか。そうかもしれないが、そうではないという思いが、この読書会を継続させている動機である。
本を読むということは、特に僕のように別段本の虫でもないような人間からすれば、それを日常化させることは簡単ではなく、きっかけがどうしても必要になる。参加者にとって読書会とは本を読むきっかけであり、学びの装置なのである。また、どの本でも必ず一回は回ってくる報告の際に、報告者となった人は、その担当個所を丁寧に読み込む必要が出てくる。ここにあって、報告という制度は、参加者に、最低一度は文章を丁寧に読み込むことを“強制する”仕掛けをもっている。いいかえれば、本の読み方には、代表的なものとして、多読と精読があるが、毎週一章という頻度で多読を実現しながらも、何回かに一回、精読をするタイミングが回ってくる意味で、僕たちは両方を経験することができる。
もうひとつさかのぼって、なぜ本を読むことが大切かという話もしたい。さきほど、これまで読んだ本を列挙したが、たとえばクリステンセン『イノベーションのジレンマ』をあなたはお読みになったことはあるだろうか。この「イノベーションのジレンマ」という言葉は、現在人口に膾炙する有名な言葉となっており、一般には、既存の大企業がイノベーションを起こせずに、新興企業の台頭によって力を失うという意味で理解されている。だが、この本を読んだことがある人ならお分かりだと思うが、原題はInnovator’s Dilemma(『“イノベーターの”ジレンマ』)なのである。つまり、イノベーションという行為自体にジレンマがあるわけではない。クリステンセンのいうジレンマとは、あるメーカー、とりわけ既存の大企業において、新興技術を採用しなければ、それを採用しつつ成長する新規参入企業にいずれマーケットで駆逐されることが明確であるのに、初期の段階ではコスト計算からどうしてもその技術を採用できないというジレンマのことを指している。つまり、既存の大企業ではイノベーターが、ジレンマに陥って行動できないのである。この詳しい仕組みについてはこの本をお読みいただくとして、以上のことからだけでも、邦訳が間違いとまではいわないにしても、適切とはいえないことが分かるだろう。このように、有名な言葉ほど「知っている気」にならずに、もう一度確認することで、適切にその概念を使うことができるようになる点で、本を読むということが大切になってくるのである。
また昨今、ビジネスのスピードに合わせる形で、物事の理解が粗雑になっている感がある。「とりあえずこれはこういうことだろう」という物事の理解の仕方で議論を進めると、それが何についてであれ、議論が混乱したときに、どこで齟齬が起こっているのか、誰も分からなくなってしまう。本を読むという作業は、特にそれが丁寧であればあるほど、ひとつひとつの理解を確実にしながら議論を進める型を身につけさせてくれる。つまり、言葉の定義や発言の背景、議論のレベルやレイヤーというものに慎重になることである。外国語文献であれば、僕たちは単数形と複数形、一般名詞と固有名詞、関係代名詞の制限用法と非制限用法など、こまかな文法の違いにも注意を払う。思い込みではなく、そこに何が書いてあるかを理解しようとする態度は、そのまま日常生活においても、相手や議論そのものに敬意を払うことにつながる。

加えて、物事の理解を粗雑にせずに相手に敬意を払いながら接することは、この複雑な社会を複雑なまま捉えようとする姿勢でもある。この世の中において、わかりやすい説明ほど暴力的なものはない。それは、一個人のうちにすら多様性を抱えているという現実を忘却し、世界を単純化する危ない指向性である。本を丁寧に読んでいけば、本が、ただ書かれているだけでなく、編まれていることが分かるだろう。その構造を読み取る姿勢を、読書は教えてくれる。
さらに、他人が薦める本を読むことの意義について。それは、知的関心に基づく自分の世界が侵略されることであり、その境界線が引き直され、定義すらも変わりうることである。僕個人の経験でいえば、自分は音楽をやっていながら、友人に勧められてアートに関する本を読むまでは、美術や舞台芸術など、音楽以外の芸術について全く無頓着であった。今では、音楽表現をほかの芸術との関連の中でとらえ直そうという態度を持つことができるようになった。また、先般世界を驚かせたイギリスのEU離脱についても、当初はイギリスの方に問題があると考えていたが(今も大枠においてその認識は変わっていない)、その離脱後に読んだ廣瀬『資本の専制、奴隷の反逆』において、EUもまた問題含みだということを、学ばされた。他人が薦める本を読み、それまで関心をもとうともしなかった世界に触れることで、人はイノベーティブな変化を経験することになる。そしてそれを繰り返すことで、僕たちはバランスの取れた人間に少しずつ近づいていく。
このように、(人と)本を読むとは、ただ知識を身につけたり、スキルを磨いたりすることに留まらない意味を持っている。僕はこのことを、「強度ある教養を身につける」と呼んでいる。課題が複雑化し、価値観が多様化する現代社会において、自分たちが軸をもって生きていくためには、まず教養が必要であるが、その教養には強度がなくてはならない。簡単にへし折れてしまうような教養は、豆知識かハウツーと呼ばれても仕方がない。そうならないためには、知識やスキルは、これまで述べてきたような思考態度とセットになっていないといけないと思う。そして読書会は、少なくとも僕たちにその素地を作ってくれているのではないか。コンビニのように情報が手に入る今の時代に、あえて机に向かい、あるいは人とひざを突き合わせて、編まれた書物を丁寧に紐解いていくことの大切さを、僕は信じている。
 註1: ショウペンハウエル『読書について 他二篇』斎藤忍随訳、岩波文庫、1960年、129頁
註1: ショウペンハウエル『読書について 他二篇』斎藤忍随訳、岩波文庫、1960年、129頁