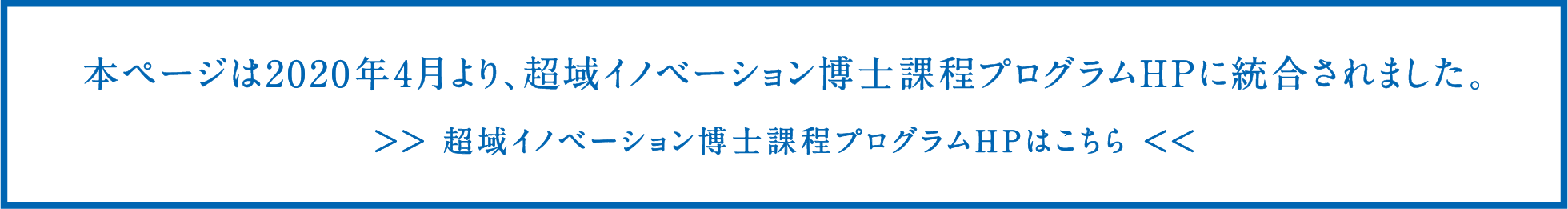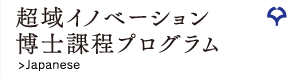Texted BY: 人間科学研究科 米田 翼
専攻:基礎人間科学 (現代思想)
専門分野:生物学の哲学、ベルクソン、individuation
3.11という未曾有の大災害から早二年が経過したものの、われわれが解決しなければならない問題はまだまだ山積みであり、それらの多くは科学技術と社会の関係をめぐる複雑なものである。本講義では、こうした〈トランス・サイエンス〉的問題(Weinberg 1972)の一つである「高レベル放射性廃棄物の処分」および「その検討委員会の人選の妥当性」に関する関連資料を事前に読み込み、ディスカッションを行い、トランス・サイエンスという問題の本質に迫ることを試みた。本稿では、私の専門の知見を交え、本講義を通して考えたことを素朴に書き綴ってみたいと思う。
■科学と社会との関係:
トランス・サイエンス的な問題が強調される以前にも、科学と社会の対話は当然意識されてきた。従来の図式では、科学者が非科学者に正しい知識を教育するという形で科学的コミュニケーションがなされた。重要なのは、そこでは科学の「絶対性」と「客観性」が無条件に前提されていたということである。このような科学的知に対する信頼は、19世紀フランスの哲学者・社会学者・数学者であるA. コントが提唱した「三段階の法則」がもたらす一つの帰結といえよう。コントによれば、われわれの認識は、神学的虚構、形而上学的抽象を経て最終的に科学的実証へと至る。このような図式は、中世における神学、17世紀における哲学、そして17世紀後半から18世紀にかけての二度の科学革命という歴史と合致する。その後、19-20世紀における物理学中心主義的な認識が形成されるにつれて、科学は次第に宗教的な決定論としてふるまうようになる。われわれの科学に対する信頼もこのような態度から抜け出しているとはいえない。今やわれわれは科学に妄信しているとすらいえるのだ。
しかし、トランス・サイエンス的な問題―BSE、遺伝子組み換え食品、そして原子力発電―が顕在化してきた昨今、科学の「絶対性」や「客観性」が揺らぎはじめている。それは、これらの問題が個々の科学技術の射程を越え出てしまっているためにほかならない。こうしたトランス・サイエンスの領域の問題を考えるためには、単に科学技術について考えるというだけでは不十分である。われわれは今こそ、「社会の中の科学技術」について考えなければならないのだ(日本第2期科学技術基本計画)。
■コントのエンジニア概念:
では、ここでわれわれは、コント的な認識のプロセスを放棄せねばならないのだろうか。いや、むしろコントに再度立ち返るべきではないか、と私は思う。先述した「三段階の法則」において、科学的実証がそれ自体で十分実践にたるものであるとコントは断言していない。そこで得られた知を真に実践的に応用するためには、科学者は人文科学的な知を切り離してはならないのだ。科学的な実証によって得られた知は帰納法的推論を用いることで、一般的な命題を抽出するが、それを事実問題もしくは個別的な問題のなかで「応用」するという真の実証は工学的な演繹の役割であるとコントは補足する。ここでいうエンジニアリングという概念は現代的な意味よりも広義のものであり、産業的のみならず社会的な水準をも考慮した全体を設計する知を意味する。それは、科学的実証から得られた合理的予測を社会の中での行為の水準に落とし込み応用することを旨とする。もちろん、こうした俯瞰的な視点を必要とする知的判断は、自然科学的な知の領野をはみ出すものである。エンジニアリングの知は人文科学者との共同によってのみ導かれるものであろう。
このようなコント的なエンジニア像こそわれわれ超域生が目指すべき一つのモデルであるように思える。それは、科学的決定論における一方向的なコミュニケーションの在り方とは別のやり方で、つまり、いわゆる理系と文系の区別なく双方向的な知的対話によって、科学技術を社会と結びつけるファシリテーター、科学知と人文知を結ぶ「媒介の専門家」である。
■科学技術のスポークスマン:
ところで、「社会の中の科学技術」を考えるときに、コント的なモデルから導出されるファシリテーター像だけで本当に十分なのであろうか。こう問いを立て直してみてもいいかもしれない。この複雑な社会に存在する断絶は、理系と文系の間の断絶のみなのか。例えば、コントの影響下で独自の科学哲学を発展させたフランスにおいては、確かに科学哲学者を中心に科学技術について議論するという土壌が比較的整っている。しかし、そのようなフランスにおいても、科学コミュニケーションが十全に行われているかというとあやしい。それは、エリート主義的伝統をもつフランスでは、科学技術をとりまく議論がアカデミックプロパーを中心に構築されるためである。この社会に横たわる深い溝は文理の断絶だけではない。政策を担う主体と市民の間の断絶にもまた亀裂が走っているのだ。
「社会の中の科学技術」を真摯に考えるとき、われわれは「公共性」をいかにして担保するかという問題に踏み込まねばならない。公共的な場をデザインするファシリテーターこそが、「媒介の専門家」の第二の水準である。それは、政策を担う主体と市民を結びつける科学技術のスポークスマンにほかならない。トランス・サイエンスという問題を提起した物理学者ワインバーグは、今日では熟議民主主義とよばれる政策決定のプロセスを提唱したが、実際にこのようなプロセスのなかで政策を担う主体と市民を媒介する専門家というのは存在しない。トランス・サイエンス的な問題を考える際、理系的な専門家だけでなく、文系的な専門家との協力が必要不可欠であるのはいうまでもないが、そこでの決定を社会に問う際、彼らと市民とを媒介する専門家もまた必要なのである。
■結びにかえて―「milieu」の専門家:
本講義において、われわれは「高レベル放射性廃棄物の処分」および「その検討委員会の人選の妥当性」をめぐって議論を交わした。そして、これらの議論の中で、コント的なエンジニアあるいは科学技術のスポークスマンという「媒介の専門家」の二つのモデルを導出することができた。オールラウンド型のリーディングプログラムである超域の学生であるわれわれは、まさにこうした視点を獲得し、社会の中での様々な断絶をつなぐ媒介者として機能することが求められている。このような媒介者はもはや単なる中間的な存在者ではなく、英語のmiddleとenvironmentの双方の意味を有するフランス語milieuという語で表現されるべきであろう。われわれに求められるのは単なるトランスレーター、仲介者としての視点だけではなく、問題全体をとりまく環境を把握できる俯瞰的な視点なのだ。
この意味で、エピステモロジーという科学史的な手法で概念の形成史を俯瞰的に記述する哲学の一分野を専門とする私は、こうしたmilieuの専門家として成長することがより求められるであろう。実際、エピステモロジーの代表的人物であるG. バシュラールおよびG. カンギレムはともに哲学者でありながらフランス国立科学研究所の所長を勤めた。彼らの哲学的な議論だけではなく、その思想の実践にもまた、多くの学ぶべきところがあるだろう。彼らは常に現実と向き合い続けてきたのだ。私が専門とする哲学者、H. ベルクソンによれば、「知性は、不連続なものしか明白に想い描かない」(『創造的進化』)。しかし、現実の世界は常に動的で生成と変化に満ちていく、とベルクソンは続ける。われわれは常に運動のただなかで思考し続けねばならないのだ。従来の哲学者にありがちな頭でっかちな机上の空論に終始してはならない。様々な運動に身を置きながら、常に現実と向き合い、生きた思想を紡ぎ出す。これこそが、超域生としての私に求められていることのように思える。